| 「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年11月6日号「日本計量新報週報デジタル版」 日本計量新報全紙面 (PDFファイル) 今月のIDとパスワードを入力して閲覧することができます。 日本計量新報の全紙面閲覧(pdf版)のID&PWをご覧ください。 2025年11月のIDとPWは次のとおりです。 ID:5168 PW:N6HDA2K8 官僚制度と計量の世界(17)を執筆するにあたり中央度量衡検定所と東京物理学校当時の様子を伝える蓑輪善蔵さまの私の履歴書を再掲載しましたところ、蓑輪善蔵さまから達者であると認められるお便りが2025年11月3日に届きましたことをお知らせ申し上げます。大正14年(1925年)生まれの方は2025年中に誕生日を迎えると100歳になります。銀座にあった中央度量衡検定所そして東京物理学校の記録をご自身の体験のままに語られたことは貴重です。 (計量計測データバンク編集部) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その1-  中央度量衡検定所。東京銀座の木挽町にあった庁舎。その後に計量研究所になり、さらに板橋区に庁舎を移した。 東京物理学校の夜学と銀座木挽町の中央度量衡検定所 大正14年生れ、佐原中学を卒業して中央度量衡検定所に入所したの男がいた。蓑輪善蔵である。中央度量衡検定所に勤務しながら蓑輪善蔵は戦前の物理学校の夜学に入学、稀なことだが苦労することなく卒業。東京大学出身の技師が幹部として働く職場で技術職として重きをなし、工業技術院計量研究所が筑波に移転するころに第四部長として働き、その後に通産省計量教習所長をつとめた。蓑輪善蔵の教習所長としての内部の職階は通産省の課長級であった。後任は通産省本省課長補佐級になり、教習所はそれ以後は別組織になって現在に至っている。東京大空襲を京橋区木挽町の中央度量衡検定所の地下室で経験した度量衡の国家公務員の手記を蓑輪善蔵がのこしている。 以下は蓑輪善蔵の手記である。 佐原で造り酒屋の分家の長男として生まれる  写真は蓑輪善蔵氏 本家は代々蓑輪由兵衛を名乗り酒造業を営んでいた 私の出生地は、幕末、精巧な実測日本地図と、このとき使用したと言われる折衷尺で有名な伊能忠敬を生んだ千葉県佐原市で、1925年3月、蓑輪仲三、雪江の長男として生まれました。私の家は分家で、本家は代々蓑輪由兵衛を名乗り酒造業を営んでいて、分家した初代が儀助、二代が善吉、三代が仲三です。本家も明治の中頃まではなかなかの羽振りだったようですが、何故か家業が傾き一気に没落してしまいました。 この時わが家の当主は1865年生まれの善吉で本家の蔵番等をして生計を立てていたようですが、本家の没落後の我が家は、ある時払いの催促なしの借金とはいえ200円の負債を持つ生活に入りました。この借金は本家の土地200坪を買い取る資金とこれから住む家の修理代(それまで蔵として使っていた所)で、本家は総てを整理して残った資産は2000円だったと聞いています。本家、分家の間柄とは武家社会の主従と同じ様なものだったのでしょうか、今考えると随分と不合理のようにも思われます。わが家の借金最後の返済は、確か1940年中学生の私が1人で親戚に届けに行き借用証書を受けとってきたと覚えています。 祖父善吉とその妻 善吉は中風を患い左足が悪く歩くのも不自由だったこともあってか、書を良くし、郡役所の書記や女学校の事務員などを勤めていました。菩提寺である日蓮宗浄国寺内にある七面大明神縁起の碑文は善吉の書によるものです。善吉には5人の弟がおりましたが東京に2人、北九州に1人いて、あとの2人は身寄りがなく我が家の墓に入っています。 善吉の先妻「くに」は佐原町の加瀬尚八の三女で、善吉には「くに」との子「みの」と「くに」死亡後の後妻「はつ」との子仲三がいますが、「はつ」が後妻にはいった時「みの」は「はつ」の実家、久住の医家沢田良安のもとに引き取られて育っています。詳しい話は聞いていませんが、「はつ」の性格が知れようと言うものです。「みの」の嫁ぎ先坂井家は今松戸市に続いています。母雪江は銀行員吉田忠蔵の長女で妹4人と弟1人がいます。雪江の母は直ぐに亡くなり、次に来た後妻も妹1人を残して他界、後の弟妹は三度目の後妻の子です。 母は女学校には入ったものの継母に大分虐められた様ですが、実家は私より10才程上の、母の弟義一が継ぎ、吉田家は佐原市浜宿に続いています。 善蔵の名は祖父から貰う 私が生まれた時、名前を何とつけるか大分揉めたようですが、結局二人の祖父善吉と忠蔵の一字づつを取って善蔵とつけたとのことで、お蔭様で字画が多く苦労したのは私でした。祖父善吉は1865年生まれ、父は1901年生まれそして私は1925年生まれで3人とも丑年でした。私が生まれて2年後に生まれた弟昭二を始め6人もの弟や妹が生まれましたので、私は早くから祖父母特に祖母「はつ」の手に移っていたのは当然のことでしょう。 祖父母の思い出 祖父との思い出は、冬は居間の炬燵に、夏はテーブルを前に同じ場所に座っていて、子供達はその傍には寄り付けませんでしたが、小学校に入学する前に祖父と2人で、当時向島区隅田町に住んでいた「みの」の嫁ぎ先坂井家を訪ねたことがありました。 祖母とは幼稚園に入るまで天気がよければ幼稚園の庭や、小野川の土手で遊び、菩提寺の日蓮宗浄国寺に併設されている清正公のお祭りの日(毎月23日)に太鼓を叩きに行ったり、天理教につれていかれたことなどがありました。 佐原の家を整理した時の遺品などを見ると祖父母は信心深かったように思えます。浄国寺に今も残る二体の浄行菩薩は由兵衛と善吉の寄付したもので、わが家にはこの浄行菩薩や不動明王などの掛軸が残っています。この頃の話でしょうか、浄国寺のお上人が私の顔を見て「この子は親、子に縁の薄い子だ」と言ったとか。 水運の集散地佐原町 私が覚えている頃の千葉県香取郡佐原町は、人口2万人程の町で利根川を挟んで千葉県側の佐原と茨城県側の北佐原とに分かれ、小学校も佐原小学校と北佐原小学校の2校がありました。千葉県側の佐原はさらに利根川に注ぐ小野川によって東側の本宿と西側の新宿とに分かれています。 伊能忠敬宅は小野川沿いの本宿側にありましたが、新しく建てた現在の忠敬記念館は小野川を隔てた新宿側に建てられています。私の家は伊能忠敬宅から300メートルほど離れた小野川の上流部分にありました。 佐原は江戸時代、利根水運による江戸への物資輸送のための集散地として栄えていました。利根川周辺から生産品の荷揚げと、江戸への輸送のため、小野川沿いには大きな店が並び、店の前の道路から川まで階段が作られていました。その中に、利根川を越えた茨城県から白瓜を購入して奈良漬を作っていた親戚(分家としての初代儀助の妻、喜舞の実家)があって、小さい時から度々使いに行っては可愛がられていました。 佐原の祭り 関東の三大祭の一つとも言われる祭りは、本宿にある八坂神社の夏祭りが7月半ばに、新宿にある諏訪神社の秋祭りが9月末に行われていました。この祭りは、各町内にある山車に7、8人のお囃子を乗せ佐原ばやしを奏でながら、街中を引き回すもので、近在からの見物客で大いに賑わったものです。山車は大きな歴史人形、藁で作った鷹や鯉などを乗せた大きなもので、本宿に約10台、新宿に約14台があります。また、今は佐原市になっていますが、香取には武神、経津主命を祭る官幣大社香取神宮があります。香取神宮のお祭りは、お田植え祭、12年毎の軍人祭、などが記憶に残っています。 佐原小学校時代 私の年代は1931年9月18日に起こった柳条湖における鉄道爆破事件即ち満州事変発端の年に小学校に入り、1937年7月7日盧溝橋で始まった日支事変の年に中学校に入り、最上級生になった1941年12月8日には第二次大戦が始まっています。物心つく頃から戦争の歩みの中に身を置いてきたことになります。 1931年に小学校に入りましたが、佐原小学校は家から200m位の所にあり、運動場も広く子供達の遊び場の1つでした。私は3月生まれの早生まれでしたので,3年生まで弱年組の男女組でした。佐原は伊能忠敬の出身地であり、小学校時代は毎年4月半ばの忠敬記念日に、諏訪公園にある銅像の写生をさせられていました。 小野川の上流には田に水を引くための堰があり、田植え時期以降になると堰は閉ざされ、その上流は2m位の深さがありました。私なども小学校2年生位から背の立たないここで泳いでいました。 男女組が解消された4年生の頃に家と小野川との間にあった水田が埋められ5、6年生用の校舎が建ちました。丁度5年生になった時その校舎が竣工し、この校舎に入ったため、この時から家の裏庭から学校に行けるようになりました。 放課後の遊びは専ら校庭でしたが、町内に年上で野球の好きな人達が何人かいたためか、近所の子を集めて野球チームが作られたのが丁度5年生の頃で、私も初めから参加させられ6年生までショートを守っていました。昭和11年の2・26事件の日は佐原でも深いところで50cmもの雪が積もっていました。 佐原中学に進む 佐原付近での中等学校は農業学校を除けば県立の銚子商業、佐原中学そして私立の成田中学でした。前にも記したように私の家は代々商人で、父は銀行員、小学校5年生の時には、5、6年生合同の算盤大会(読上げ算と加減算)があって上位に入ったりもし、また本家の人達は皆銚子商業でしたので、私も銚子商業かとも思っていましたが、通学時間や交通費などのこともあり、佐原中学校になりました。 1937年約150人ほどが佐原中学校に入学しましたが、その内35人程が佐原小学校からの入学者でした。この辺での通学は下宿を含めた徒歩以外に自転車、汽車、バス、船ですが、船通学などはこの辺ならではのことでしょう。 軟式庭球部に入る 佐原中学校には剣道部、柔道部、野球部、籠球部、弓道部、庭球部(軟式)、陸上部、射撃部、そして端艇部などがありました。人気のあった端艇部はボートの老朽化からこの年に廃部になってしまいました。利根川で行うボートレースは夏の風物詩の一つで、見物人は堤防にあふれ、たくさんの出店が並びました。 小学校から野球はよくやっていましたので、同級生の中では上手だった筈で、野球部の上級生からは執拗に入部を勧誘され、脅されもしましたが何故か軟式庭球部に入っていました。部活動とは別に剣道と柔道が正課になっていて、そのどちらかに所属しなければならず私は剣道部でした。 1938年でしたか、7月に台風による大水があり、畳を上げて道具類をその上に上げ、弟妹達を母の実家に避難させたりしましたが、床下に水が入り乾くまで大変でした。このとき利根川近くの養鯉場も水をかぶり多くの鯉が逃げ、水が入った水田で鯉を釣る人で賑わったりしていました。 中学も3、4年生頃まで勉強もぼちぼち、祖父か父が読んだものか、漢文や古文の本やその解説書などがあり、十八史略や徒然草、土佐日記などを読み始めたのもこの頃で、物理、数学よりは興味を持っていました。 映画「愛染かつら」 遊ぶことには不自由しませんでしたが、テニスに明け暮れる中で霞ヶ浦、利根川での水泳、鮒釣りそして「愛染かつら」の映画にうつつを抜かしていました。この当時中学生の映画館入りはご法度でしたが、「愛染かつら」の時などは教師も来ていて補導されることもありませんでした。家から200mも歩けば鮒釣り場があり、暇があれば釣りに行っていた頃もありました。 事教練と「非国民」 軍事色が強くなる中、配属将校の権力が校長を凌ぐほどになり、教練の授業での体罰は殴る、蹴るなどは当たり前でした。1940年、当時の5年生が紀元2500年を記念して宮城前で行進したこともあり、この頃から毎月朔日の早朝、香取神宮に参拝させられました。1941年中学も最上級生となり、軍事教練も多くなり、富士の裾野や下志津練兵場などでの軍事教練も行われるようになっていました。 12月8日の米英への宣戦布告により軍事体制は更に加速されていきました。 中学5年生の時、忘れもしません、私を非国民と罵(ののし)ったまだ若かった国語の先生がいました。漢文を教えていたのですが、教科書の順序を飛ばして講義するので、講義の順序を前もって教えておいてほしい、と言ったら、途端にがなり始め、果ては非国民にまで発展してしまいました。卒業式の日にでも、殴ってやろうかと思っていましたが、間もなく結核になり学校に来なくなってしまいました。 天野清技師との機縁で中央度量衡検定所に入所 中検、天野清技師(1) この頃、中央度量衡検定所(以後中検と略す)の天野清技師は日本科学史への執筆のため度量衡の歴史の調査をしていて、佐原の漢学者清宮秀堅の著わした地方新書度量権部(我が国度量衡の歴史を書いたもの、元老院刊行)の調査と、伊能忠敬が使ったという折衷尺調査のため何度か佐原に来ていました。 佐原中学校の事務員でもあった伊達牛助氏は伊能忠敬の研究者で、天野技師と面識があり、そんな事から、伊達牛助氏を通じ佐原中学校での中検職員の募集があったものと思われます。 清宮秀堅の子孫は、代々清宮利右衛門を名乗る旧家で、私の家とも付き合いがあったし、現在の当主は小学、中学の同級生で、中学校では同じ軟式テニス部、毎日一緒に練習で汗を流していたのに、清宮秀堅のことをつい数年前まで知らなかったとは迂闊もひどい話でした。 天野技師の誘いで中検に この頃の我が家は、祖父母、両親、それに弟妹4人の9人家族、父親1人の稼ぎでは余裕のある筈もなく、家も狭くなり、私は鼻の詰まりそうな生活から逃げるべく中学を卒業したら早速と外に出ることを考えていました。佐原などには適当な就職先も無く、また人手不足の時代でもあり就職は極めて楽な状態で、中検への就職も天野技師が佐原中学校に来た時にお会いすることだけで決まってしまいました。 普通は3月の卒業後4月から勤めに出ますが、人不足の時代で、中学卒の就職の場合繰り上げて卒業を認め、卒業年の1月から勤められることになっていました。私は3月上旬の卒業式が終わった後上京、3月中は向島区隅田町にあった父の姉「みの」の嫁ぎ先坂井家に、4月からは神田美土代町の父の従兄蓑輪甲子三氏宅に厄介になりました。 「雇を命じ、日給1円25銭給与す。中央度量衡検定所勤務を命ず」の辞令 ここは神田橋の近くで、神田橋から都電に乗れば直ぐに数寄屋橋、中検まで歩いて10分足らず、入学することにしていた学校にも歩いて直ぐ、足場のよいところでした。1942年3月20日過ぎ、京橋区木挽町の中検に天野清技師を訪ね、直ぐに庶務室の岡田嘉信技師の下に連れていかれ、勤め始めの日を2、3日後からと決めて戴きました。 佐原中学から私と前林四良さんの2人が中検に入所しましたが、前林さんは直ぐに辞めて警察官になってしまいました。3月31日付けで「雇を命じ、日給1円25銭給与す。中央度量衡検定所勤務を命ず」という辞令を貰い、勤め始めました。 中検、天野清技師(2) この日給は月の日数分のことで、大の月なら31日分で38円75銭のことです。この頃は既に主食は配給制で外での食事には外食券が必要な時代で、私は3食とも外食することとしていましたが、1日の食事代は1円もあれば足りた時代です。この年中検に入所した中学校卒業者は6、7人いた筈ですが、残ったのは1月から勤めていた栗島茂吉さん、茂木一雄さんと私の3人になってしまいました。 量衡器係に配属 中検に入所して最初に配属されたのは量衡器係、係長は桑田幸男さん、次席が中谷昇弘さんだったように思います。係員は15、6人位だったと思いますが、10人程が女子職員で男子職員の約半数が都内に出張していました。残された2、3人の男子職員はメスフラスコ、メスシリンダー、ガラス製ますの検定と金剛砂を使って吹き付ける証印押し(足踏み式)でした。 入所したばかりですので、ガラス製ますの検定を教えてもらいながら、日がな1日証印押しをしていた時もありました。小柳さん、安達さん、千田さんなどと言う先輩女子職員は等比天秤を前に向き合い、衡量法によってピペット、ビュレットなどの検定をしていました。 直ぐに計量教習生に 4月も後半になった頃、計量教習生の試験があるから受けてみたらと、量衡器係女子職員の責任者であった松本恵美子さんから話があり、係長の桑田さんに申し出て、計量教習が何なのか、どんな問題が出るのもわからない中で、数日後の試験を受けました。出来はあまり良くありませんでしたが合格の通知があり、5月から始まる計量教習の授業を受けることになりました。 計量教習の内容 計量教習は中堅職員の養成を目的にした中検独自のもので、中学校卒業者を対象に、数学、物理、電気などの基礎学科と度量衡器、計量器についての知識と技術を習得させるため、約1年間、勤務時間のすべてを当てて教授するものでした。 計量教習は大学や高等専門学校を卒業して中検に入所する人が少なかったことにも起因しているようで、1937年(第1期)から開始され44年(第8期)まで続きました。 1937年の第1期には服部章二さん、木戸作二さん、堀越義国さんなど、第2期には庄司行義さん、中谷昇弘さん、上野三郎さん、勝田仁郎さんなど、第3期には小泉袈裟勝さん、森田ふみさんなど、第4期には川村竹一さん、立川喜久夫さん、小川了さん、大岸修一さん、など、第5期には高橋照二さん、小島鹿蔵さん、後藤信雄さん、中村政人さん、松本恵美子さんなどがおります。 第6期教習生10名 1943年3月に終了した私達の第6期教習生は10名程でしたが、そのうち長く計量に残っていた方々は、東京本所では飯島肇さん、栗島茂吉さん(後大阪支所)、茂木一雄さん、大坂支所の西岡輝治さん、広島出張所の高橋直倫さん(後広島県計量検定所)、福岡支所の松永三男さんなどでした。教習生側の代表は本所の斎藤勝雄さんでしたが、教習後半の1ヶ月ほどは、飯島さんと共に病気休養していました。 教授陣と先輩 教授陣は教習責任者で熱学が米田麟吉技師、物理学が玉野光男技師、数学が天野清技師、電気が佐藤朗技師、衡器が岡田嘉信技師と北村品市技手、精密測定が朝永良夫技師と山本保技手、製図が小池清技手、水力学・機構学・化学実験などが外来講師、実習では酒井五郎技手、竹内喜一郎技手の方々だったと思いました。 朝出勤してから帰るまで、1日中の授業でしたので私などはまるっきり学校の延長気分でした。中学を出たばかりの私が最年少で皆に良くしていただきましたが、特に、飯島さん、高橋さん、松永さんには可愛がって頂き、いつも3人の後ろについていました。 中央度量衡検定所は夜学通いを奨励 日大の高等工学校に 中央度量衡検定所(中検)は職員に夜学に行くことを奨励していて、通学にはいろいろな便宜を与え、退庁時間も夜学に間に合う時刻で良いとされていました。夜学に行っていない人がいると、「何故行かないのか」と言われ、多くの人が中学校、専門学校、大学などの夜学に通っていました。 私も4月から日本大学の高等工学校機械科に通っていましたが、家は代々商人で父は銀行員、中学に入るときも銚子商業か佐原中学かで迷わされていた程なのに、何故理科系の学校を選んだのか今になってもよく分りません。ただ、この時代、理科系優遇の措置がとられ、国としての要求も多くなっていました。同じ機械科に佐原中学の3年ほど先輩で都庁に勤めていた根本さんが通って来ていたのは、驚きでもありました。 ボート部に籍を置く この学校は夜学であってもボート部があり、郷愁もあって入部し、授業が終わったあと屋上でスライド式の道具を使い、エイトを漕ぐ練習をしていました。夏休みになって、艇庫に近い向島に合宿所を設営、朝の4時頃から2時間ほどエイトを漕ぎ、朝食後都電で銀座4丁目迄行き、木挽町の中検まで通う日々を2週間程続けました。 日曜日にはエイトを漕いで埼玉県の方まで上ったりしたものです。合宿の終わりに上級生と浅草で打ち上げをしましたが、ビールの大ジョッキが54銭、大ビンが32銭だったように思いましたが、初めての面白い経験をしました。殆どの人がへべれけで、まともだったのは酒の飲み方を知らない私のほか二人ほどでした。上級生を合宿所まで連れて行くのが大変でした。 東京物理学校に入学 10月頃までは日大の夜学にも通っていましたが、高等工学校は準専門学校であったし、17才の私に来年からボート部のキャプテンをやれ等と言われた事もあり、さらに、中検には東京物理学校の卒業生が多いし、在学している人も多かったこともあって、翌年から東京物理学校にゆくこととし、夜学は退学してしまいました。 何故東京物理学校の卒業生が多いのか、その時は分かりませんでしたが、後に、1891年公布された度量衡法施行に伴う、度量衡取締公務員を養成するため、その教育を東京物理学校に委託したことに起因していることを知りました。中検には岡田さんの明治専門学校出を除けば技師は総て東大出で、専門学校出の多くは物理学校出でした。 私は夜学に行かなくなると、時間を持て余すようになり、万世橋にあった洋画専門の映画館シネマパレスに毎週通い、ここで「格子なき牢獄」などのフランス映画を見たり、飯島さん達に付いて見物や遊びに連いて回っていました。 中検技師の面々 中央度量衡検定所(中検)は1933年の庶務細則では、本所に1部、2部、3部と庶務係を置くとの規程がありましたが、私が入所した頃は、研究、検査、検定等を技師が分担処理していた模様で、一度も技師を呼ぶのに部長という言葉を聞いたこともありませんでした。 長さ測定における光波干渉測定で世界的な研究成果をあげた渡辺襄氏が二代目所長で、その下に、本所には米田麟吉技師、今泉門助技師、玉野光男技師、岡田嘉信技師、天野清技師、佐藤朗技師と属兼技手の友森肇さん、大阪支所長に糸雅俊三技師、福岡支所長に的場鞆哉技師が居られ分担して総ての指揮をとっていたようでした。私などから見れば雲の上の方々ですが、先輩達は皆「さん」づけで畏まっているようなところはみえませんでした。 私なども1年間教えて頂いたこともあって、親しみも感じられ中検時代から「さん」づけで呼ばせていただき、それが続いていました。この頃は食糧事情も厳しくなってきていましたが、まだ外食券なども比較的に余裕があり,銀座にも牡丹、若松などの喫茶店も開いていました。 教習修了祝いに箱根に 一年間の教習が終わりに近づいた1943年3月、教習責任者の米田さんと神奈川県度量衡検定所長の岩崎栄さんとのお世話で神奈川県度量衡検定所小田原支所の見学と、教習生だけによる箱根湯本での一泊旅行を計画実行していただきました。 確か吉池だったように思いますが、このときは大阪の西岡さんが引率者になっていました。計量教習の終了と同時に、支所の人たちは支所に帰り、本所でもそれぞれの部署に戻りましたが、私は量衡器係ではなく、新しく比較検査係に配属されました。 比較検査係に配属 比較検査係は今で言えば基準器検査係で検定に使う当時で言う標準器の器差検査の実施部署で、幹部は玉野光男さん、天野清さん、佐藤朗さんの各技師の下に物理学校出の北村品市さん、竹内喜一郎さんの両技手と後に属となった技手で、教習が一緒だった斎藤勝雄さんがおられ、それに雇員の坂本熈さん、石沢邦治さん、大越正夫さん、宮坂主計さんなどと女子職員では井上みよ子さん、疋田ますさん、神田真砂子さん、松本多美子さんなどのベテラン先輩連がおられ、女子職員の方々は分銅、ます、化学用体積計の基準器の検査を、その他の器種を男性が担当していました。 男子職員が毎日行っていた業務は湿式ガスメータの検査で、私も先輩達に教えられ早速と3灯、5灯の検査を手伝い始めました。 月給貰いながら物理学校へ この4月から飯田橋の東京物理学校にも通い始めましたし、親戚にいつまでも迷惑を掛けていられませんので、石沢さんの世話で千駄ヶ谷の石沢さんと同じ家に下宿することになりました。東京物理学校への入学は、無試験で、戸籍謄本があれば高等師範科に行かれますが、無いと本科で私は本科でした。これは、早くから父親に戸籍謄本を頼んでいたのですが、出願期限までに届かなかったためでした。 月給45円、授業料8円 千駄ヶ谷での下宿代は朝、夕の2食ついた4畳半で月33円、月給が45円、物理学校の授業料が8円、これで、飢えもせずに生活できたのは、ボーナスと出張旅費とのお陰でしょう。下宿に移った当座南京虫に悩まされたのには閉口しました。 この下宿には入所直後に配属された量衡器係の職員で、この時は退職していた東山利一さんが時折訪ねてきていました。中検には短い期間しか勤めていなかったようでしたが、彼は右翼の大物影山正治氏に心酔していて影山塾にも入っていたようで、終戦の日に宮城前で割腹してしまいました。下宿から新宿までは歩いても直ぐで、時間を作っては遊びに行っていました。 東京物理学校の夜学 1943年4月には艦載機による東京初の空襲がありましたが庶務室の窓から見ていた事が思い出されます。物理学校では夜学の1年生が2000人で1組500人、さすがの大部屋も遅く行けば座るところもなく先生の声も聞こえませんでした。 しかし物理や数学は計量教習での講義の復習が多く、1年の時の出席は半分くらいでした。6月になった頃、石沢さんのお姉さんが伊豆大島のため朝館におられ、大越さんと遊びに行くのに無理にご一緒をお願いし、下駄で三原山に登り、途中で下駄が半分に割れ往生したのを思い出します。 石沢さんは私を連れて行くのに反対で、物理学校は試験が大変だから、大島などへ行っていては駄目だとのことでした。このとき、いま大島に帰られた白井岩一さんのお母さんにお目にかかった様に思います。 ガスメーター校正の思い出 学校が夏休みになるのを待って,守衛室の隣にあった11tのタンクによるステーションメーター(大型湿式ガスメーター)の校正を行うことになりました。責任者は玉野さん、そして竹内さん、北村さんに坂本さん達、私も参加し手伝いをしました。 測定は温度が一定する夜半過ぎから明け方まで、夜10時頃再び出勤する玉野さんは、私などには珍しかったホットケーキを持参されたりして、測定に立ち会っておられました。 測定の流速が遅いときは待ち時間が長くなるので、本を読んだり囲碁をしたりしていましたが、私は玉野さんと将棋を指したことが忘れられません。囲碁はまだ出来ませんでしたし、将棋も小学校の頃に遊んだ程度、時間を持て余していた私の相手をして頂いたものと思っています。 当然のことながら一度も勝たして貰えませんでした。10日程かかったこの測定が終わった頃、度量衡の指導者として中国の天津に居られた江浦重利さんが中国の人1人と共に、中検見学のためか1週間ほど比較検査係に通ってこられたことがありました。 秋に入ると、今度は小型の標準湿式ガスメーターの校正を本館2階の中庭で、縦型のベル型ガスホルダーを使って行いました。 丁度この頃が国内標準の確認時期にあったようです。ガスメーターの校正が終わった後は佐藤さんの仕事即ち原器室でH型標準直尺の水中での比較を手伝うようになっていました。地下室には横動比較機もあった筈ですのに原器庫の前での作業でした。 私たち入所1年程の男性4、5人が、ガスメーター、水道メーターの出張検定要員確保のため、白藤静一さん(後岩手県に移られました)から検定の実習を受け、都内出張に行く事ができるようになったのもこの頃です。 検査出張手当で助かる 出張先は、品川製作所、金門製作所、園池製作所、東京ガス、都の水道局その他で、毎日30人以上もの人々が出張していました。都内出張の手当は半日当で、技手が1円25銭、雇員が1円でした。この旅費は私の生活に随分役立ちました。 岡田さんを長とした使用中の水道メーター調査が行われたのもこの頃で、成績はあまり良くなかったと思いますが、戦争に必要な金属不足を踏まえ、この結果から有効期間の延長になったようです。 確かこの年の冬からだったと思いますが、鉄供出のため、暖房がスチームからダルマストーブに切り替えられ、地下室からの石炭運びが男の仕事になりました。温度の急激な変化は測定に影響を与えるため、部屋の中央部付近にストーブ1つが置かれていただけでした。 休み時間になると先輩の女子職員達は半卓の下にガスコンロを置き、毛布を掛けておしゃべりをしていましたが、良くその中に入れて貰っていました。そんな時天野さんが脇を通ることがあっても、笑っていましたが、当時渡辺所長の主義なのか、男女間の垣根は非常に高いもので、所内では口を聞くのもご法度で、女性はお嬢様、男は何処の馬の骨か分からないと言ったとかで、年配の林さんと言う女子職員の監督者もいて目を光らせていました。 物理学校の2年生に進級 坂本さんが出征したのもこの頃で、壮行会をするため天野さんと、今のJRで吉祥寺の坂本さんの家までご一緒したことがありました。 物理学校は進級が非常に厳しくて簡単には2年になれなかった。私のとき1年生が2000 人位いて2年になったのは 500人です。私より前は2000人の中から200人ぐらいしか2年になれていません。私のときは戦争の最中だから理科系の人材を育てなくてはいけないということで、進級させる範囲が広がったようです。 翌1944年はじめ天野さんや竹内さんなどから勉強の便宜を与えられたお陰で、物理学校も運良く2年生になることが出来ましたが、比較検査係の皆さんからお祝いを言われました。 ご褒美とお仕置き 2年生になったということだけで比較検査係から渡辺所長直属の調査研究係に移されました。 物理学校出の小池清さんの下で、私と一緒に物理学校に通っていた「馬見塚勝」さんが出征した後任の様でしたが、後で聞いた話では、蓑輪君にはその仕事は向かないと、天野さんはこの移動には反対されたとの事でした。 小池さんは物理学校夜学で製図の講義を担当していて、私も生徒の1人でした。調査研究係の係長は近藤幸造さんで、ここでは当然のことながら定常的な仕事はなく、ブロックゲージをベンガラや酸化クロムで磨き平面を出すことや、ニッケル鍍金の実験などをさせられていましたが、3週間くらい経ったときのこと、昼の15分前頃にブンゼンバーナーで飯盒の飯を炊いていたとき、突然と渡辺所長が入ってこられ、途端に雷が落ちてきました。 中検の感化院に 直ぐ謝ればよかったのにと後で言われましたが、見つかってしまったことだし、今更言い訳もと頭を下げて黙っていましたところ、逆鱗に触れたのでしょう、翌日、中検の感化院と称されていた(後から聞かされた話)係長が谷川盈科さんの計圧器係に配置換えになりました。谷川さんから聞かされた話では、所長が玉野さんに、あいつは、馬鹿だか図々しいのかわからん奴だと、言ったとか。 [資料] 明治専門学校 明治専門学校は山川健次郎と安川財閥の創始者である安川敬一郎らによって、1909年(明治42年)福岡県北九州市に私立の旧制工業専門学校として創立された。1921年(大正10年)に官立に移管され、1949年(昭和24年)に国立九州工業大学になる。明治専門学校には支援と特別講義などのため尾崎行雄、犬養毅、大隈重信、原敬、長岡半太郎、手島精一、益田孝、渋沢栄一、團琢磨、藤山雷太他など訪れている。 米田麟吉、芝亀吉、小口太郎の三氏 米田麟吉氏は『日本計量新報』のwebサイトに掲載している、蓑輪善蔵氏の「私の履歴書」と齊藤勝夫氏の「私の履歴書」のなかに登場している。小口太郎は1919(大正8)年、東京帝国大学理学部物理学科に入学しており、当時1学年20名か30名であった理学部学生の同級生として芝亀吉、米田麟吉の両氏がいた。小口太郎の名前は科学者としての業績よりも、三高の水上部員時代に作詞した「琵琶湖周航の歌」で知られており、生家のある長野県岡谷市の諏訪湖畔、釜口に銅像が建っている。米田麟吉のことを中央度量衡検定所の後輩の高橋凱は「上下に隔てのない、また後に残さない、本当にさっぱりした気持ちの良い方でした」と日本計量新報に追悼文を寄せている。同じく中央度量衡検定所の後輩の高田誠二は「英文、仏文の論文や資料をこしらえるときに先生のお世話になった方は数しれないだろう。論文の英文抄録をでっち上げる場合、初心者はたいてい「これこれについてしかじかの条件下で何々が」と長々しい収吾をしつらえ、文末に「……が研究された」と書く。先生それをサッとご覧になって「頭が重いよ」と批評なさる。つまり「主語が長すぎるよ」という意味なのだ.。芝亀吉は徳島中学校をでて、のち1918年(大正7年)に第三高等学校を卒業している。熱学、熱力学の権威であり、計量管理協会の事業にも深く関わっている。米田麟吉は東京府立一中から第八高等学校に進んでいる。3人とも1922年(大正11年)に東京帝国大学理学部物理学科を卒業している。米田麟吉は電気試験所に入所、大正15年に中央度量衡検定所に転任、後に第一部長、第二部長などを歴任して1961年(昭和36年)に退官して工学院大学教授に転じている。芝亀吉は東京大学教授などを勤めた後に東洋大学教授となっている。。 私の履歴書 簔輪善蔵(計量計測データバンクweb版) 本稿は日本計量新報に連載された文章をweb版である計量計測データバンクで取り扱った初版web版2002年4月7日付(第2440号)から2003年6月1日付(第2493号)までのものです。 オーラルヒストリー 蓑輪善蔵氏インタビュー 「計量制度に係わっ て 69 年」 目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介 関連論説-その3-3,000万人国家日本と生活の有り様の予測 夏森龍之介 関連論説-その2-インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介 関連論説-その1-経済からみた日米戦争と国力差、ウクライナ戦争の終着点 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(23) 第二次大戦突入と焦土の敗戦「なぜ戦争をし敗れたのか」 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(22) 結核で除隊の幹部候補生 外務省職員 福島新吾の場合 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(21) 戦争と経済と昭和天皇裕仁 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(20) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(19) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(18) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(17) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(16) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(15) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(14) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(13) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(12) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(11) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(10) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(9) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(8) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(7) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(6) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(5) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(4) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(3) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(2) 執筆 夏森龍之介 官僚制度と計量の世界(1) 執筆 夏森龍之介  ナナカマドは葉をすべて落してカラマツの黄葉を背景にその深紅が心を射た。仕方ないかな、しかし撮影したかったのだとレンズを向けた。 門が閉まるのは11月20日(木)である。日本有数の高原道路は諏訪と佐久を結ぶ国道299号線。春に夏に秋に高原道路を超える。佐久から諏訪からそれぞれ旅行にあわせて。 11月3日(月)の祭日には諏訪の高原には薄雪がきた。10月28日には水鉢に厚さ3cmの氷。4月には佐久から。6月にも同じ。今回は諏訪から麦草峠を越えた。道には雪が残っていて夏タイヤは横に滑って車の破損を予想させる動きをした。 佐久側に回った景色はそれが北八ヶ岳の南側ということもあって晩秋のそれであった。二週間ほど前に撮影をためらったナナカマドは葉をすべて落してカラマツの黄葉を背景にその深紅が心を射た。仕方ないかな、しかし撮影したかったのだとレンズを向けた。大きな実。梢を北からの渡り鳥が横切って行った。 雪の残るカラマツ林の道路は東山魁夷の池の風景を思わせた。池の淵には白馬が配されていた。その御射鹿池(みしゃかいけ)はこの道の諏訪側にある。標高2,100mのモミの木の道路に女鹿が一頭姿を見せた。その後には鹿の群れを見た。夏の鹿の子模様が消えて焦げ茶の冬毛に変っていた。 小海町のスーパーで水とお結びと唐揚げを買って忙しい旅を続けるのだ。 大事な写真はフィルムカメラで撮影すると大石芳野女史 甲斐鐵太郎 相手は常人ではないと警戒していることが大事 ああついにまた来たか。この10年いや30年ほどまともな担当公務員が続いていたのに 遂に来た。いかれたのが来るとその在任期間はその公務員が担当する業務は動かないか後退する。まともなことを言って抗(あらが)っても事実上意味をなさない。任期の終了する二年間は業務の進展をあきらめることになる。後任者が去っていった者に対して開口一番適切な評価を下す。その在任中になされたであろうことに対して業務にかかわった団体や民間企業の担当者へのねぎらいの言葉なのである。 役所に勤務する人への評価はその役所の内部でかなりの程度定まっていて、そのことを皆が知っている。まともではないから世間とかかわる業務に従事させてはならないと周囲は一致していても人事はお構いなしに年功序列のたらいまわしをする。当の本人はまともな募りでいても同僚と上司あるいは部下はそのような評価はしていない。官庁における人事の制御は下部機構には弱くしか働かない。 自己保身と役所の権限を過度に使う、この人はやはりおかしいという人物を時どきか、ある周期で見かける。計量管理協会が会員事業所を大きく減らし、計量時事川柳で「出版と講習で喰う計管協」が大絶賛された。役員事業所が日本計量機器工業連合会会員の質量計事業所などで占められていたことが事業実態を示していた。計量行政室の担当課長補佐は同会専務理事の責任を追求し、単独事業体としての存続に難色を示した。同会はこの時から10年ほどして事業体としての存続を断念することになった。計量管理協会存続の大事な最後のころに協力したのが矢野宏であり、同氏との縁で田口玄一が品質工学を講習事業の講演者となったが尽力は功を奏さなかった。 当時の通産省も計量管理に関係した計量管理協会の事業に進行に有効な策を提案し或いは講じることができなかった。半分生え抜きの専務理事は退職して会長会社の東京支店長の東大工学部卒業者が定年後に就任した。会計は見かけ上は奇麗な形で運営を続けたものの上昇の機運を迎えることができなかった。同じことが関係する工業団体でもなされた。監督官庁への配慮だけが優先した事業運営がなされていたが生え抜きの事務局員には不評の専務理事であり二期務めて退任した。 計量事業に関係する団体とその監督官庁との間では時に異常性のある担当者に振り回される。国鉄民営化に伴って計量行政室の係長職に転任した者がいた。役人には適さないヤクザ者であり、叙勲申請でこの人物を頼って振り回された経営者がいた。この経営者が最後に残した言葉は「お金と役職は引き換え」であった。叙勲には団体役員の経歴が必須ということで柄に合わない役職に就いていたのが滑稽ではあった。 大型ハカリの検定に伴う型式承認制度の制定当初、小規模事業者はこの男を頼りにした。国鉄から移ってきたヤサグレの係長がその部署のトップである者に威嚇的に別の事案で承認を求める様子を見ている。 規則と目的に従って事業を推進するのが公共機関職員のあるべき姿である。人の健康ということで心のそれが崩れている者は多い。この欄でときどき触れているのはこのような人に出会った時への備え、同じことだが警戒心である。相手が常人と思うと腹が立つが世の中に認められない異常な人と思えばやり過ごすことができる。くわばら、くわばらと何時も自分に言い聞かせていたい。 ハカリの指定定期検査機関制度運営と財政の性質 ├経済産業省幹部異動履歴(2025年10月21日付、ほか7月1日付、7月5日付、7月6日付、7月7日付、9月30日付、(10月21日付)) (2025/10/22 経済産業省幹部名簿/METI Officials List) (https://www.meti.go.jp/intro/data/pdf/list_ja.pdf) 経済産業省幹部名簿は人事異動に伴って「2025/10/22 経済産業省幹部名簿」が更新されます。下欄の名簿は2025/10/22公開の経済産業省幹部名簿です。(計量計測データバンク編集部) 10月21日付 松山泰浩 2025年日本国際博覧会協会運営基盤調整統括室長兼会場運営局長→官房政策立案総括審議官 兼 首席国際博覧会統括調整官 茂木正 官房政策立案総括審議官 兼 席国際博覧会統括調整官→内閣官房内閣審議官 兼 内閣官房長官秘書官事務取扱 筑紫正宏 電力基盤整備課長→大臣秘書官事務取扱 井上博雄 首相秘書官→官房付 荻野洋平 城内国務大臣秘書官事務取扱→官房付 曽根哲郎 伊東国務大臣秘書官事務取扱→官房付 西川和見(官房サイバー・セキュリティ情報化審議官 兼 経済安全保障政策統括調整官兼半導体戦略統括調整官)→兼 官房政策統括調整官=製造産業局担当 添田隆秀 大臣秘書官事務取扱→電力基盤整備課長 香山弘文 官房審議官=製造産業局担当兼官房政策統括調整官=重点政策高度化担当兼経済安全保障政策統括調整官→首相秘書官 宮井彩 文化創造産業課文化創造産業海外需要開拓室長兼文化創造産業企画調整官→小野田国務大臣秘書官事務取扱 尾坂北斗 通商政策企画調整官→内閣官房副長官秘書官 猪又真介(地域産業基盤整備課長)→兼 地域産業基盤整備課工業用水道計画官 川口征洋 2025年日本国際博覧会協会運営統括室担当部長 兼 広報・プロモーション局担当部長→貿易振興課長 佐久秀弥(資源エネルギー庁電力基盤整備課電力流通室長)→兼 資源エネルギー庁電力基盤整備課電力供給室長 吉川尚文 貿易振興課長→辞職・国際協力機構理事へ 北沢善幸 地域産業基盤整備課工業用水道計画官→辞職 岩男健佑 資源エネルギー庁電力基盤整備課電力供給室長→辞職 長窪芳史 資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課制度企画調整官→退職 7月7日付 杉江一浩(経済安全保障政策課長)→免兼 情報調査室長 日原正視 日本貿易振興機構ベルリン事務所次長→貿易経済安全保障局参事官=経済安全保障担当 兼 経済安全保障政策課情報調査室長 中西友昭(イノベーション・環境局総務課長)→免兼 産業技術法人室長 鈴木章文 復興庁→産業技術法人室長 岩男健佑 大臣官房付→資源エネルギー庁電力基盤整備課電力供給室長 矢口麻衣 大臣官房付→ジュネーブ国際機関日本政府代表部参事官 植田一全 大臣官房付→辞職・日本貿易振興機構ドバイ事務所 中富大輔 資源エネルギー庁電力供給室長→辞職・北海道経済部次長 兼 GX推進局長 7月6日付 池山成俊 経済産業研究所理事→通商政策局通商交渉官 兼 商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官 阿部康幸 大臣官房付→辞職・新エネルギー・産業技術総合開発機構ワシントン事務所長 田中宗介 大臣官房付→辞職・新エネルギー・産業技術総合開発機構シリコンバレー事務所長 7月5日付 井上誠一郎 官房審議官=経済産業政策局担当→辞職・経済産業研究所理事へ 7月1日付 藤木俊光 経済産業政策局長→事務次官 佐々木啓介 内閣府官房審議官=経済安全保障担当→総括審議官 兼 首席地方創生担当政策統括調整官 藤本武士 消費者庁政策立案総括審議官→福島原子力事故処理調整総括官 畠山陽二郎 資源エネルギー庁次長 兼 首席最終処分政策統括調整官 兼 首席GX推進戦略統括調整官 兼 首席エネルギー・地域政策統括調整官 →経済産業政策局長 兼 首席GX推進戦略統括調整官 成田達治 総括審議官 兼 経済安全保障政策統括調整官→貿易経済安全保障局長 伊藤禎則 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長→脱炭素成長型経済構造移行推進審議官 兼 GXグループ長 龍崎孝嗣 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官 兼 GXグループ長 →資源エネルギー庁次長 兼 首席最終処分政策統括調整官 兼 首席エネルギー・地域政策統括調整官 河西康之 内閣官房内閣審議官=新しい資本主義実現本部事務局長代理→特許庁長官 山本和徳 中小企業庁事業環境部長→中小企業庁次長 飯田祐二 事務次官→辞職 小野洋太 特許庁長官→辞職 新居泰人 福島原子力事故処理調整総括官 兼 首席能登復興担当政策統括調整官→出向・復興庁統括官へ 福永哲郎 貿易経済安全保障局長 兼 首席経済安全保障政策統括調整官→出向・内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官へ 飯田健太 中小企業庁次長→出向・消費者庁政策立案総括審議官へ 西田光宏 脱炭素成長型経済構造移行投資促進課長→大臣官房付 呉村益生 航空機武器産業課長→大臣官房付 西川和見 貿易経済安全保障局総務課長→大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 竹田憲 大臣官房参事官→大臣官房調査統計グループ長 大貫繁樹 大臣官房会計課長→大臣官房秘書課長 安田篤 イノベーション・環境局総務課長→大臣官房参事官=技術・高度人材戦略担当 吉村直泰 内閣官房副長官補付内閣参事官→大臣官房総務課長 若月一泰 デジタル庁統括官付参事官→大臣官房会計課長 村上貴将 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長→大臣官房業務改革課長 細川成己 産業保安・安全グループ保安政策課長→大臣官房審議官=産業保安・安全、電力・ガス取引監視等委員会事務局担当 田岡卓晃 特許庁総務課長→産業保安・安全グループ保安政策課長 前田博貴 資源エネルギー庁原子力立地政策室長兼原子力広報室長→電力安全課長 森本将史 新エネルギー・産業技術総合開発機構シリコンバレー事務所長→製品安全課長 宮本岩男 中小企業庁中小企業政策調整官 兼 地域経済産業政策統括調整官 →地方創生担当政策統括調整官 兼 イノベーション・環境局イノベーション政策統括調整官 中野剛志 大臣官房参事官→地方創生担当政策統括調整官 中村智 大臣官房総務課政策企画委員→産業構造課長 鮫島大幸 中小企業庁取引課長→産業組織課長 松田洋平 政策調整官=経済産業政策局担当→産業創造課長 豊田原 商取引監督課長→投資促進課長 日野由香里 産業創造課長→地域経済産業政策課長 猪又真介 関東経済産業局総務企画部長→地域産業基盤整備課長 高山成年 農林水産省官房輸出促進審議官→大臣官房審議官=通商政策局・農林水産品輸出担当 田中将吾 資源循環経済課長→通商戦略課長 白井俊行 資源エネルギー庁大臣官房国際課長→欧州課長 高木重孝 製造産業局生活製品課長→北東アジア課長 藤沢秀昭 大臣官房付→国際経済部長 西脇修 防衛装備庁官房審議官→大臣官房審議官=貿易経済安全保障局担当 田中伸彦 経済安全保障政策調整官=技術担当→経済安全保障政策統括調整官 稲邑拓馬 製造産業局総務課長→貿易経済安全保障局総務課長 浅井洋介 投資促進課長→貿易管理課長 中西友昭 産業組織課長→イノベーション・環境局総務課長 石川浩 日本貿易振興機構シンガポール事務所産業調査員→イノベーション創出新事業推進課長 中野真吾 内閣官房副長官秘書官→国際標準課長 福本拓也 イノベーション政策統括調整官→大臣官房審議官=脱炭素成長型経済構造移行推進担当 清水淳太郎 業務改革課長→脱炭素成長型経済構造移行投資促進課長 三牧純一郎 内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム参事官→資源循環経済課長 畑田浩之 大臣官房参事官=技術・高度人材戦略担当→大臣官房審議官=製造産業局担当 玉井優子 経済産業政策局地域経済産業政策調整官→製造局総務課長 渡辺宏和 日本貿易振興機構ニューヨーク貿易保険事務所長→生活製品課長 木村拓也 資源エネルギー庁省エネルギー課長→航空機武器産業課長 金指寿 情報産業課長→商務情報政策局総務課長 渡辺琢也 情報処理基盤産業室長→情報技術利用促進課長 南部友成 日本貿易振興機構ニューヨーク事務所産業調査員→情報産業課長 乃田昌幸 資源エネルギー庁原子力損害対応総合調整官→商取引・消費経済政策課長 西川奈緒 国際標準課長→サービス政策課長 梶直弘 産業構造課長→文化創造産業課長 福田光紀 資源エネルギー庁ガス市場整備室長→ヘルスケア産業課長 広瀬大也 新エネルギー・産業技術総合開発機構事業統括部グリーンイノベーション基金室長→生物化学産業課長 浦田秀行 大臣官房審議官=製造産業局担当→北海道経済産業局長 横田純一 貿易管理課長→北海道経済産業局資源エネルギー環境部長 上野麻子 中国大使館参事官→資源エネルギー庁国際資源エネルギー戦略統括調整官 大江健太郎 大臣官房付→資源エネルギー庁長官官房国際課長 小林大和 大臣官房秘書課長→資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 那須良 資源エネルギー庁政策課長→資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長 福永佳史 北東アジア課長→資源エネルギー庁省エネルギー課長 永井岳彦 資源エネルギー庁燃料供給基盤整備課長→資源エネルギー庁資源・燃料部政策課長 東哲也 通商戦略課長→資源エネルギー庁燃料供給基盤整備課長 吉瀬周作 資源エネルギー庁原子力政策課長→資源エネルギー庁電力・ガス事業部参事官=エネルギー制度改革担当 多田克行 資源エネルギー庁原子力基盤室長 兼 革新炉推進室長 兼 原子力技術室長→資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政策課長 吉沢隆 経済産業研究所総務ディレクター→特許庁総務部長 降井寮治 内閣官房内閣情報調査室参事官→特許庁秘書課長 亀井明紀 公正取引委員会事務総局企業取引課長→特許庁総務課長 北村弘樹 特許庁審査第三部長→特許庁審査第一部長 小松竜一 特許庁審判部審判課長→特許庁審査第二部長 諸岡健一 特許庁審査第二部長→特許庁審査第三部長 仁科雅弘 特許庁審査第四部審査長=首席・電子商取引・経営システム→特許庁審査第四部長 野仲松男 特許庁審査第一部長→特許庁審判部長 黒田浩司 中小企業庁小規模企業振興課長→中小企業庁官房総務課長 坂本里和 内閣官房内閣審議官=新しい資本主義実現本部事務局次長→中小企業庁事業環境部長 佐伯徳彦 文化創造産業課長→中小企業庁企画課長 橋本泰輔 ヘルスケア産業課長→中小企業庁金融課長 小高篤志 資源エネルギー庁戦略企画室長→中小企業庁取引課長 山崎琢矢 大臣官房総務課長→中小企業庁経営支援部長 前田了 電力安全課長→中小企業庁経営支援課長 荒木太郎 内閣官房内閣人事局参事官→中小企業庁小規模企業振興課長 神崎忠彦 商務情報政策局総務課長→出向・内閣官房副長官補付内閣参事官へ 殿木文明 大臣官房審議官=産業保安・安全、電力ガス取引監視等委員会事務局担当 兼 大臣官房調査統計グループ長 →出向・内閣官房内閣審議官=国家安全保障担当 兼 内閣府官房審議官=経済安全保障担当へ 下世古光可 地域経済産業政策課長→出向・内閣官房行政改革推進本部事務局参事官へ 柏原恭子 国際経済部長→出向・内閣官房内閣審議官へ 西森雅樹 特許庁秘書課長→出向・内閣官房観光立国推進室参事官へ 田尻貴裕 大臣官房審議官=脱炭素成長型経済構造移行推進担当 →出向・内閣官房内閣審議官=新しい資本主義実現本部事務局次長へ 貴田仁郎 中小企業庁官房総務課長→出向・内閣官房新しい資本主義実現本部事務局参事官へ 浦上健一朗 大臣官房審議官=国際博覧会担当→出向・内閣府官房審議官=経済財政運営担当へ 佐々木雅人 エネルギー・地域政策統括調整官→出向・内閣府官房審議官=原子力防災担当へ 太田三音子 サービス政策課長→出向・内閣府知的財産戦略推進事務局参事官へ 柴山豊樹 中小企業庁経営支援課長→出向・公正取引委員会事務総局経済取引局企業取引課長へ 岡田智裕 中小企業庁経営支援部長→出向・デジタル庁統括官付審議官へ 市川紀幸 地域産業基盤整備課長→出向・復興庁統括官付参事官へ 宮部勝弘 中小企業庁事業環境部企画課長→出向・福島復興局次長へ 藤田健 欧州課長→出向・文化庁文化経済・国際課長へ 依田学 大臣官房審議官=通商政策局農林水産輸出担当→出向・農林水産省大臣官房付へ 滝沢豪 特許庁総務部長→出向・防衛装備庁官房審議官へ 西垣淳子 大臣官房政策統括調整官=経済産業局担当兼中小企業庁官房中小企業政策統括調整官=DX・EBPM担当 →出向・政策研究大学院大学特任教授へ 野沢泰志 中小企業庁金融課長→出向・東京大学産学協創推進本部特任研究員 兼 スタートアップ推進部長へ 佐藤猛行 製品安全課長→辞職・経済産業研究所総務コーディネーター 内田了司 情報技術利用促進課長→辞職・情報処理推進機構上席執行役員 下田裕和 生物化学産業課長→辞職・日本医療研究開発機構調整役 西村秀隆 サイバーセキュリティ・情報化審議官→辞職 瓜生和久 基準認証政策統括調整官→辞職 油科壮一 特許庁審査第四部長→辞職 田村聖子 特許庁審判部長→辞職 桑原智隆 イノベーション創出新事業推進課長→退職 ├2025/10/22 経済産業省幹部名簿/METI Officials List 大臣・副大臣・大臣政務官・次官・経済産業審議官 大臣 赤澤亮正 あかざわりょうせい 副大臣 山田賢司 やまだけんじ 副大臣 井野俊郎 いのとしろう 大臣政務官 小森卓郎 こもりたくお 大臣政務官 越智俊之 おちとしゆき 経済産業事務次官 藤木俊光 ふじきとしみつ 経済産業審議官 松尾剛彦 まつおたけひこ 経済産業大臣秘書官(事務取扱) 筑紫正宏 ちくしまさひろ 大臣官房 官房長(併)公文書監理官 片岡宏一郎 かたおかこういちろう 総括審議官 佐々木啓介 ささきけいすけ 政策立案総括審議官(併)首席国際博覧会統括調整官 松山泰浩 まつやまやすひろ 技術総括・保安審議官 湯本啓市 ゆもとけいいち 審議官(政策総合調整担当) 服部桂治 はっとりけいじ 秘書課長 大貫繁樹 おおぬきしげき 人事企画官 廣瀬浩三 ひろせこうぞう 人事審査官 中嶋重光 なかじましげみつ 企画調査官(労務担当)(併) 中嶋重光 なかじましげみつ 参事官(技術・高度人材戦略担当)(併)危機管理・災害対策室長 安田篤 やすだあつし 総務課長 吉村直泰 よしむらなおやす 国会業務室長 谷澤厚志 たにざわあつし 国会連絡室長(併)国会事務連絡調整官 山本剛 やまもとつよし 業務管理官 天野博之 あまのひろゆき 文書室長 田守光洋 たもりみつひろ 公文書監理室長 渡邊賢一 わたなべけんいち 文書管理官(併) 田守光洋 たもりみつひろ 広報室長 折居直 おりいすなお 地方調整室長 金谷明倫 かなだにあきみち 政策審議室長 片山弘士 かたやまひろし 会計課長(併)監査室長 若月一泰わかつきかずひろ 経理審査官 細谷賢二 ほそやけんじ 企画官(会計担当) 島田肇 しまだはじめ 監査官 末光英勝 すえみつひでかつ 厚生企画室長 北村敦司 きたむらあつし 厚生審査官 西沢正剛 にしざわまさたけ 業務改革課長(併)政策立案推進室長(併)組織経営改革統括調整官 村上貴将 むらかみたかまさ 情報システム室長 上田圭一郎 うえだけいいちろう 統括情報セキュリティ対策官 中山和泉 なかやまいずみ デジタル・トランスフォーメーション室長(併) 上田圭一郎 うえだけいいちろう 情報公開推進室長(併) 田守光洋 たもりみつひろ 個人情報保護室長(併) 田守光洋たもりみつひろ EBPM推進総括企画調整官 橋本淳二郎 はしもとじゅんじろう 大臣官房調査統計グループ 調査統計グループ長 竹田憲 たけだけん 参事官(調査統計グループ・総合調整担当) 樋本諭 とよもとさとる 統計企画室長 渡邉幹夫 わたなべみきお 統計情報システム室長 馬場勝 ばばまさる データマネジメント推進室長 杵渕敦子 きねぶちあつこ 業務管理室長 皆川幸夫 みながわゆきお 経済解析室長 相田政志 あいだまさし 統括統計官 林雅樹 はやしまさき 統括統計官 菅原浩志 すがわらひろし 構造・企業統計室長 田邉敬一 たなべけいいち 鉱工業動態統計室長 田村秀一 たむらひでかず サービス動態統計室長 鈴木実 すずきみのる 大臣官房福島復興推進グループ 福島原子力事故処理調整総括官(併)廃炉・汚染水・処理水特別対策監 藤本武士 ふじもとたけし 福島復興推進グループ長(併)廃炉・汚染水・処理水特別対策監(併)処理水損害対応支援室長 辻本圭助 つじもとけいすけ 原子力事故災害対処審議官 宮﨑貴哉 みやざきたかや 廃炉・汚染水・処理水対策室現地事務所長 紺野貴史 こんのたかし 審議官(原子力防災担当)(併)福島復興推進政策統括調整官 佐々木雅人 ささきまさと 原子力被災者生活支援チーム審議官(併)福島復興推進グループ付 佐野究一郎 さのきゅういちろう 資源エネルギー庁長官官房国際原子力技術特別研究官(併)資源エネルギー庁長官官房国際資源エネルギー技術戦略調整官(併)廃炉・汚染水・処理水特別対策監 八木雅浩 やぎまさひろ 政策調整官(併)総合調整室長 松井拓郎 まついたくろう 政策調整官(福島イノベーション・コースト構想担当) 蘆田和也 あしだかずや 企画調査官(福島復興推進担当) 岩谷邦明 いわたにくにあき 業務管理室長 小倉聡美 おぐらさとみ 福島広報戦略・風評被害対応室長(併)福島芸術文化推進室長 大星光弘 おおぼしみつひろ 福島新産業・雇用創出推進室長(併)福島事業・なりわい再建支援室長 松山大貴 まつやまだいき 企画官 杉山佳弘 すぎやまよしひろ 原子力被災者生活支援チーム参事官(併)福島新エネ社会構想推進室長 遠藤量太 えんどうりょうた 原子力損害対応総合調整官(併)原子力損害対応室長 廣山奨平 ひろやましょうへい 原子力発電所事故収束対応室長 加賀義弘 かがよしひろ 東京電力福島第一原子力発電所事故廃炉・汚染水・処理水対策官 宮嶋秀一 みやじましゅういち 参事官 須賀正志 すがまさし 企画官 駒田拓 こまだたく 原子力発電所事故収束対応調整官 植松健 うえまつたけし 大臣官房産業保安・安全グループ 産業保安・安全グループ長(併) 湯本啓市 ゆもとけいいち 審議官(産業保安・安全担当) 細川成己 ほそかわなるみ 業務管理室長 大野亜希子 おおのあきこ 保安政策課長 田岡卓晃 たおかたかあき 業務改革推進室長(併) 田岡卓晃 たおかたかあき 高圧ガス保安室長 牟田徹 むたとおる ガス安全室長 石津さおり いしづさおり 産業保安企画室長(併)制度審議室長(併) 田岡卓晃 たおかたかあき 電力安全課長 前田博貴 まえだひろたか 電気保安室長 正影夏紀 まさかげなつき 鉱山・火薬類監理官 佐藤努 さとうつとむ 火薬専門職 橋森武志 はしもりたけし 石炭保安室長(併) 佐藤努 さとうつとむ 製品安全課長 森本将史 もりもとまさし 製品事故対策室長 望月知子 もちづきともこ 化学物質管理課長(併)化学物質リスク評価室長 大本治康 おおもとはるやす 化学物質安全室長 内野絵里香 うちのえりか 化学兵器・麻薬原料等規制対策室長 濱口千絵 はまぐちちえ オゾン層保護等推進室長 今村真教 いまむらまさのり 化学物質管理企画官 水野紀子 みずののりこ 化学物質リスク評価企画官(併) 内野絵里香 うちのえりか 経済産業政策局 経済産業政策局長(併)首席GX推進戦略統括調整官 畠山陽二郎 はたけやまようじろう 首席地方創生担当政策統括調整官(併) 佐々木啓介 ささきけいすけ 審議官(経済産業政策局担当) 河野太志 こうのふとし 政策統括調整官(経済産業政策局担当)(併) 竹田憲たけだけん 地方創生担当政策統括調整官 宮本岩男 みやもといわお 地方創生担当政策統括調整官 中野剛志 なかのたけし 業務管理官室長 藤山優子 ふじやまゆうこ 総務課長 松野大輔 まつのだいすけ 政策企画官 立石裕則 たていしひろのり 調査課長(併)企業財務室長 田代毅 たしろたけし 産業構造課長 中村智 なかむらさとし 経済社会政策室長(併) 高木悠一 たかぎゆういち 産業組織課長 鮫島大幸 さめしまひろゆき 競争環境整備室長 池田陽子 いけだようこ 知的財産政策室長 中山英子 なかやまえいこ 産業創造課長 松田洋平 まつだようへい 産業資金課長(併)投資機構室長 河原圭 かわはらけい 産業人材課長 今里和之 いまざとかずゆき 未来人材戦略室長 高木悠一 たかぎゆういち 企業行動課長 能村幸輝 のうむらこうき 企業会計室長(併) 松田洋平 まつだようへい 投資促進課長(併)対日投資総合相談室長 豊田原 とよだけん 投資交流調整官 天野富士子 あまのふじこ 地域経済産業政策課長 日野由香里 ひのゆかり 統括地域活性化企画官 大野理 おおのおさむ 地域産業基盤整備課長(併)沖縄振興室長 猪又真介 いのまたしんすけ 工業用水道計画官(併) 猪又真介 いのまたしんすけ 通商政策局 通商政策局長(併)首席ビジネス・人権政策統括調整官 荒井勝喜 あらいまさよし 審議官(通商政策局担当) 小見山康二 こみやまやすじ 審議官(通商政策局担当)(併) 田中一成 たなかかずしげ 審議官(通商戦略担当) 辻阪高子 つじさかたかこ 審議官(通商政策局・農林水産品輸出担当) 髙山成年 たかやまなりとし 通商交渉官(併) 池山成俊 いけやましげとし 通商交渉官(併) 田村英康 たむらひでやす 特別通商交渉官(併) 田中一成 たなかかずしげ 特別通商交渉官(併) 寺西規子 てらにしのりこ 業務管理官室長 井澤俊和 いざわとしかず 総務課長 山口仁 やまぐちじん デジタル通商ルール室長(併) 森川純 もりかわじゅん ビジネス・人権政策調整室長 宮崎由佳 みやざきゆか 通商渉外調整官 花輪晃二 はなわこうじ 国際知財制度調整官 田内幸治 たうちこうじ 戦略輸出交渉官 田村英康 たむらひでやす 通商金融国際交渉官 中村正大 なかむらせいだい 通商戦略課長 田中将吾 たなかしょうご 企画官桑波田啓之くわはたひろゆき 企画調査室長 依田圭司 よだけいじ 貿易振興課長 川口征洋 かわぐちゆきひろ 貿易振興企画調整官 田邉浩之 たなべひろゆき 技術・人材協力室長 下川徹也 しもかわてつや 通商金融課長(併)国際金融交渉室長 加来芳郎 かくよしろう 資金協力室長 山田聡 やまださとし 貿易保険監理官 名倉和子 なぐらかずこ 米州課長 藤井亮輔 ふじいりょうすけ 中南米室長 中山保宏 なかやまやすひろ 欧州課長 白井俊行 しらいとしゆき ロシア・中央アジア・コーカサス室長(併)通商政策企画調整官 石井秀彦 いしいひでひこ 中東アフリカ課長 渡邉雅士 わたなべまさし アフリカ室長 加藤健治 かとうけんじ アジア大洋州課長 羽田由美子 はたゆみこ 企画官 渡辺一行 わたなべいっこう 企画官 朝倉大輔 あさくらだいすけ 東アジア経済統合推進室長 谷査恵子 たにさえこ 南西アジア室長 島野敏行 しまのとしゆき 北東アジア課長 髙木重孝 たかぎしげたか 韓国室長 原充 はらみつる 国際経済部 国際経済部長(併)ビジネス・人権政策統括調整官 藤澤秀昭 ふじさわひであき 参事官(総括) 寺西規子 てらにしのりこ 国際経済紛争対策室長 森川純 もりかわじゅん 国際法務室長 西村祥平 にしむらしょうへい 通商交渉調整官(併) 谷査恵子 たにさえこ 経済連携課長 内野宏人 うちのひろと 経済連携交渉官 長﨑太祐 ながさきだいすけ アジア太平洋地域協力推進室長 宮崎拓夫 みやざきたくお 貿易経済安全保障局 貿易経済安全保障局長 成田達治 なりたたつじ 審議官(貿易経済安全保障局担当) 西脇修 にしわきおさむ 審議官(貿易経済安全保障局・国際技術戦略担当) 中西礎之 なかにしもとゆき 経済安全保障政策統括調整官(併) 西川和見 にしかわかずみ 経済安全保障政策統括調整官 田中伸彦 たなかのぶひこ 業務管理官室長 星幸彦 ほしゆきひこ 総務課長 稲邑拓馬 いなむらたくま 参事官(経済安全保障担当)(併)情報調査室長 日原正視 ひはらまさみ 参事官(国際担当) 堀江雅司 ほりえまさし 経済安全保障国際室長 相部信宏 あいべのぶひろ 情報保全室長 岡本亮 おかもとりょう 経済安全保障政策課長 杉江一浩 すぎえかずひろ 企画官(経済安全保障戦略情報分析担当) 椛島伸也 かばしましんや 政策企画官(情報調査担当) 竹原美佳たけはらみか 技術調査・流出対策室長 山下浩司 やましたこうじ 貿易管理部 貿易管理部長 猪狩克朗 いがりかつろう 貿易管理課長(併)電子化・効率化推進室長 淺井洋介 あさいようすけ 原産地証明室長 中本亮介かもとりょうすけ 貿易審査課長(併)野生動植物貿易審査室長 中尾圭介 なかおけいすけ 農水産室長(併)野生動植物貿易審査企画調整官 内田剛 うちだつよし 特殊関税等調査室長 森井一成 もりいかずなり 安全保障貿易管理課長(併)制度審議室長 末森洋紀 すえもりひろき 国際投資管理室長 門野勉 かどのつとむ 安全保障貿易国際室長(併) 森洋紀 すえもりひろき 安全保障貿易検査官室長 臺則彦 だいのりひこ 安全保障貿易審査課長 安倍暢宏 あべのぶひろ 統括安全保障貿易審査官 小塩平次郎 おしおへいじろう イノベーション・環境局 イノベーション・環境局長(併)首席スタートアップ創出推進政策統括調整官 菊川人吾 きくかわじんご 審議官(イノベーション・環境局担当) 今村亘 いまむらわたる イノベーション政策統括調整官(併) 宮本岩男 みやもといわお イノベーション政策統括調整官(併) 福本拓也 ふくもとたくや 業務管理官室長 芦立勝博 あしだてかつひろ 総務課長 中西友昭 なかにしともあき イノベーション政策上席企画調整官 飯村亜紀子 いいむらあきこ イノベーション推進政策企画室長 井上俊樹 いのうえとしき 成果普及・連携推進室長(併) 井上俊樹 いのうえとしき 産業技術法人室長 鈴木章文 すずきあきふみ 国際室長 渡部博樹 わたなべひろき イノベーション政策課長 武田伸二郎 たけだしんじろう イノベーション推進制度企画調整官 中井太二郎 なかいたいじろう フロンティア推進室長 吉田修一郎 よしだしゅういちろう 量子産業室長(併) 武田伸二郎 たけだしんじろう 大学連携推進室長 川上悟史 かわかみさとし イノベーション創出新事業推進課長 石川浩 いしかわひろし スタートアップ推進室長 富原早夏 とみはらさやか スタートアップ国際連携企画調整官 澤田佳世子 さわだかよこ 研究開発課長 大隅一聡 おおすみかずあき 研究開発調整官 黒田隆之助 くろだりゅうのすけ 研究開発企画調査官(併) 鈴木章文 すずきあきふみ 研究開発投資促進室長(併) 大隅一聡 おおすみかずあき 基準認証政策課長 有馬伸明 ありまのぶあき 国際標準化交渉官 猿橋淳子 さるはしあつこ 国際連携担当調整官(併) 渡部博樹 わたなべひろき 知的基盤整備推進官(併) 鈴木章文 すずきあきふみ 基準認証調査広報室長 小嶋誠 こじままこと 計量行政室長 仁科孝幸 にしなたかゆき 国際標準課長 中野真吾 なかのしんご 国際標準化調整官 大出真理子 おおでまりこ 国際電気標準課長 小太刀慶明 こだちよしあき イノベーション・環境局GXグループ 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官 伊藤禎則 いとうさだのり GXグループ長(併) 伊藤禎則 いとうさだのり 審議官(脱炭素成長型経済構造移行推進担当) 福本拓也 ふくもとたくや 業務管理官室長 竹内祐二 たけうちゆうじ 環境政策課長 中原廣道 なかはらひろみち GX推進企画室長 河野孝史 こうのたかし 地球環境対策室長 町井弘明 まちいひろあき 参事官(併)環境経済室長 若林伸佳 わかばやしのぶよし 環境金融室長 鬼塚貴子 おにつかたかこ 環境金融企画調整官 本橋貴行 もとはしたかゆき 脱炭素成長型経済構造移行投資促進課長 清水淳太郎 しみずじゅんたろう エネルギー・環境イノベーション戦略室長 金井隆幸 かないたかゆき 資源循環経済課長 三牧純一郎 みまきじゅんいちろう 資源循環経済課環境企画調整官(国際資源循環担当) 高橋幸二 たかはしこうじ 環境管理推進室長 濱坂隆 はまさかたかし 製造産業局 製造産業局長 伊吹英明 いぶきひであき 審議官(製造産業局担当) 田中一成 たなかかずしげ 審議官(製造産業局担当) 畑田浩之 はただひろゆき 政策統括調整官(製造産業局担当)(併) 西川和見 にしかわかずみ 業務管理官室長 中尾直子 なかおなおこ 総務課長 玉井優子 たまいゆうこ 参事官(サプライチェーン強靱化担当)(併)サプライチェーン強靭化政策室長 髙木美香 たかぎみか 企画調査官 桂誠一郎 かつらせいいちろう 製造産業戦略企画室長 荒川洋 らかわひろし 製造産業GX政策室長(併) 玉井優子 たまいゆうこ 通商室長(併) 玉井優子 たまいゆうこ 鉱物課長 山口雄三 やまぐちゆうぞう 採石対策官(併) 松本暢之 まつもとのぶゆき 金属課長 鍋島学 なべしままなぶ 金属技術室長 松本暢之 まつもとのぶゆき 企画官(国際担当) 久森委芳 ひさもりともよし 素材産業課長 土屋博史 つちやひろし 革新素材室長 山田純市 やまだじゅんいち アルコール室長(併) 土屋博史 つちやひろし 企画調査官 菊池孝憲 きくちたかのり 生活製品課長 渡邉宏和 わたなべひろかず 企画官(地場産品担当)伊藤 裕美いとうゆみ 住宅産業室長 潮崎雄治 しおざきゆうじ 産業機械課長(併)製造産業DX政策企画調整官 須賀千鶴がちづる ロボット政策室長 石曽根智昭 いしぞねともあき 素形材産業室長 大今宏史 おおいまひろふみ 国際プラント・インフラシステム・水ビジネス推進室長 粂田香 くめたかおる 自動車課長 伊藤政道 いとうまさみち 参事官(自動車担当)(併)自動車戦略企画室長 前田洋志 まえだひろし 企画調査官(自動車通商政策担当) 細沼慶介 ほそぬまけいすけ 企画官(自動車リサイクル担当) 宮越朗 みやこしあきら モビリティDX室長 黑籔誠 くろやぶまこと 車両室長 須藤義治 すどうよしはる 航空機武器産業課長 木村拓也 きむらたくや 企画官(防衛担当) 古市茂 ふるいちしげる 航空機部品・素材産業室長 西山正 にしやまただし 次世代空モビリティ政策室長(併) 古市茂 ふるいちしげる 宇宙産業課長 髙濵航 たかはまわたる 商務情報政策局 商務情報政策局長 野原諭 のはらさとし 審議官(商務情報政策局担当) 奥家敏和 おくやとしかず 審議官(IT戦略担当) 渋谷闘志彦 しぶやとしひこ サイバーセキュリティ・情報化審議官(併)半導体戦略統括調整官 西川和見 にしかわかずみ 業務管理官室長 吉田悦子 よしだえつこ 総務課長 金指壽 かなざしひさし 国際室長 猪飼裕司 いかいゆうじ デジタル戦略室長(併) 猪飼裕司 いかいゆうじ 情報経済課長 守谷学 もりやがく デジタル取引環境整備室長 岩谷卓 いわやすぐる 情報政策企画調整官 永野志保 ながのしほ アーキテクチャ戦略企画室長 緒方淳 おがたじゅん サイバーセキュリティ課長 武尾伸隆 たけおのぶたか サイバーセキュリティ制度企画室長(併) 武尾伸隆 たけおのぶたか 国際サイバーセキュリティ企画官 橋本勝国 はしもとかつくに 情報技術利用促進課長 渡辺琢也 わたなべたくや デジタル高度化推進室長 河﨑幸徳 かわさきゆきのり デジタル経済安全保障企画調整官(併) 渡辺琢也 わたなべたくや デジタル人材政策室長 迫田章平 さこだしょうへい 地域情報化人材育成推進室長(併) 河﨑幸徳 かわさきゆきのり 情報産業課長 南部友成 なんぶともしげ 情報処理基盤産業室長(併) 迫田章平 さこだしょうへい AI産業戦略室長(併) 渡辺琢也 わたなべたくや デバイス・半導体戦略室長 清水英路 しみずひでみち 高度情報通信技術産業戦略室長(併) 南部友成 なんぶともしげ 電池産業課長 青木洋紀 あおきひろき 商務情報政策局商務・サービスグループ 商務・サービス審議官(併)商務・サービスグループ長 南亮 みなみりょう 審議官(商務・サービス担当) 浅井俊隆 あさいとしたか 商務・サービス政策統括調整官 森田健太郎 もりたけんたろう 商務・サービス政策統括調整官 池山成俊 いけやましげとし 商務・サービス政策統括調整官 島上聖司 しまがみせいじ 商務・サービス政策統括調整官 江澤正名 えざわまさな 大阪・関西万博統括調整官(併) 田中一成 たなかかずしげ 大阪・関西万博統括調整官(併) 森田健太郎 もりたけんたろう 参事官(商務・サービスグループ担当) 寺本恒昌 てらもとつねまさ 商務・サービス政策調整官 池谷巌 いけやいわお 業務管理官室長 福田純子 ふくだじゅんこ 流通政策課長 平林孝之 ひらばやしたかゆき 大規模小売店舗立地法相談室長物流企画室長(併) 平林孝之 ひらばやしたかゆき 商取引・消費経済政策課長(併)商取引監督官 乃田昌幸 のたまさゆき 商取引検査室長 福岡浩二 ふくおかこうじ 消費者相談室長(併) 乃田昌幸 のたまさゆき 消費経済企画室長(併) 乃田昌幸 のたまさゆき 商品市場整備室長(併)商品先物市場整備監視室長(併)商取引監督官 鈴木貴詞 すずきたかし サービス政策課長 西川奈緒 にしかわなお サービス産業室長 関日路美 せきひろみ 教育産業室長(併) 西川奈緒 にしかわなお 企画官(教育産業担当) 柳橋幸裕 やなぎはしゆきひろ スポーツ産業室長(併) 西川奈緒 にしかわなお 文化創造産業課長 梶直弘 かじなおひろ 伝統的工芸品産業室長 山口徳彦 やまぐちのりひこ 参事官(併)博覧会推進室長 奥田修司おくだしゅうじ 大阪・関西万博国際室長 菅野将史 すがのまさふみ 大阪・関西万博企画室長 伊万里全生 いまりぜんしょう 国際博覧会上席企画調整官 舟木健太郎 ふなきけんたろう ヘルスケア産業課長(併)国際展開推進室長 福田光紀 ふくだみつのり 企画官(ヘルスケア産業担当) 小野聡志 おのさとし 医療・福祉機器産業室長 大石知広 おおいしともひろ 生物化学産業課長 廣瀨大也 ひろせひろや 生物多様性・生物兵器対策室長 小林正寿 こばやしまさとし 電力・ガス取引監視等委員会事務局 事務局長 新川達也 しんかわたつや 審議官(電力・ガス取引監視等委員会事務局担当)(併) 細川成己 ほそかわなるみ 業務管理室長 安田瑞穂 やすだみずほ 総務課長 田上博道 たのうえひろみち 総合監査室長 高橋章 たかはしあきら 取引監視課長 栗谷康正 くりややすまさ 取引制度企画室長 石井孝裕 いしいたかひろ ネットワーク事業監視課長 黒田嘉彰 くろだよしあき ネットワーク事業制度企画室長(併)総括企画調整官(併) 黒田嘉彰 くろだよしあき 統括ネットワーク事業管理官 中橋広至 なかはしひろし 経済産業局 北海道経済産業局長 浦田秀行 うらたひでゆき 東北経済産業局長 佐竹佳典 さたけよしのり 関東経済産業局長 佐合達矢 さごうたつや 中部経済産業局長 寺村英信 てらむらひでのぶ 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(併)大臣官房政策調整官(北陸地域担当) 向野陽一郎 こうのよういちろう 近畿経済産業局長 信谷和重 のぶたにかずしげ 中国経済産業局長 林揚哲 はやしようてつ 四国経済産業局長 吉田健一郎 よしだけんいちろう 九州経済産業局長 星野光明 ほしのみつあき 産業保安監督部 北海道産業保安監督部長 山下宜範 やましたたかのり 関東東北産業保安監督部東北支部長 川村伸弥 かわむらしんや 関東東北産業保安監督部長 溝田健志 みぞたたけし 中部近畿産業保安監督部長 小池勝則 こいけかつのり 中部近畿産業保安監督部近畿支部長 苦瓜作 にがうりさく 中国四国産業保安監督部長 金子健 かねこけん 中国四国産業保安監督部四国支部長 岡田俊也 おかだとしや 九州産業保安監督部長 樫福錠治 かしふくじょうじ 那覇産業保安監督事務所長 髙須賀邦充 たかすがくにみつ 資源エネルギー庁 資源エネルギー庁長官 村瀬佳史 むらせよしふみ 次長 龍崎孝嗣 りゅうざきたかつぐ 首席最終処分政策統括調整官(併) 龍崎孝嗣 りゅうざきたかつぐ 首席エネルギー・地域政策統括調整官(併) 龍崎孝嗣 りゅうざきたかつぐ 資源エネルギー政策統括調整官 山田仁 やまだひとし 資源エネルギー政策統括調整官(併 ) 木原晋一 きはらしんいち エネルギー・地域政策統括調整官(併) 佐々木雅人 ささきまさと エネルギー・地域政策統括調整官 吉村一元 よしむらかつもと 国際資源エネルギー戦略統括調整官 上野麻子 うえのあさこ 国際資源エネルギー戦略統括調整官(併) 永井岳彦 ながいたけひこ 長官官房(資源エネルギー庁) 総務課長 曳野潔 ひきのきよし エネルギー制度改革推進総合調整官(併) 小川要 おがわかなめ エネルギー制度改革推進総合調整官(併) 吉瀬周作 きちせしゅうさく エネルギー制度改革推進企画調整官(併) 佐久秀弥 さきゅうひでや 会計室長 濵崎勝 はまさきまさる 予算管理官 根本政一郎 ねもとせいいちろう 戦略企画室長 後藤靖博 ごとうやすひろ 脱炭素電源立地企画調整官(併)需給政策室長(併)調査広報室長 森本要 もりもとかなめ 業務管理官 木根昌広 きねまさひろ 国際資源エネルギー戦略調整官 粕谷直樹 かすやなおき 国際課長 大江健太郎 おおえけんたろう 海外エネルギーインフラ室長(併)企画官(国際カーボンニュートラル政策担当) 吉野欣臣 よしのよしおみ 省エネルギー・新エネルギー部(資源エネルギー庁) 省エネルギー・新エネルギー部長 小林大和 こばやしひろかず 政策課長(併)熱電併給推進室長(コジェネ推進室) 那須良 なすりょう 再生可能エネルギー主力電源化戦略調整官(併) 小栁聡志 こやなぎさとし 系統整備・利用推進室長(併) 古川雄一 ふるかわゆういち 新エネルギーシステム課長 山田努 やまだつとむ 省エネルギー課長 福永佳史 ふくながよしふみ 新エネルギー課長 日暮正毅 ひぐらしまさき 再生可能エネルギー推進室長 菊島淳治 きくしまじゅんじ 風力政策室長 古川雄一 ふるかわゆういち 風力事業推進室長 福岡功慶 ふくおかのりよし 水素・アンモニア課長 廣田大輔 ひろただいすけ 水素・燃料電池戦略室長 宇田川法也 うだがわのりや 資源・燃料部 資源・燃料部長 和久田肇 わくだはじめ 政策課長(併)海洋政策企画室長 永井岳彦 ながいたけひこ 国際資源戦略室長 長谷川洋 はせがわひろし 地熱資源開発室長 小林貴成 こばやしたかしげ 鉱業管理官 沼舘建 ぬまだてたける 資源開発課長 長谷川裕也ゆうや 石炭政策室長 畑下潔 はたしもきよし 燃料供給基盤整備課長 東哲也 あずまてつや 燃料流通政策室長 甲元信宏 こうもとのぶひろ 企画官(石油・液化石油ガス備蓄政策担当) 荒井智裕 あらいともひろ 燃料環境適合利用推進課長 刀禰正樹 とねまさき CCS政策室長(併)企画官(CCS政策担当) 慶野吉則 けいのよしのり 電力・ガス事業部(資源エネルギー庁) 電力・ガス事業部長 久米孝 くめたかし 政策課長 小川要 おがわかなめ 参事官(エネルギー制度改革担当) 吉瀬周作 きちせしゅうさく 制度企画調整官 木村純 きむらじゅん 制度企画調整官(併) 佐久秀弥 さきゅうひでや 電源地域整備室長 小町僚明 おまちともあき 電力産業・市場室長 小栁聡志 こやなぎさとし ガス市場整備室長 迫田英晴 さこたひではる 電力基盤整備課長 添田隆秀 そえだたかひで 電力供給室長(併) 佐久秀弥 さきゅうひでや 電力流通室長 佐久秀弥 さきゅうひでや 原子力政策課長 多田克行 ただかつゆき 原子力国際協力推進室長(併) 上野麻子 うえのあさこ 原子力基盤室長(併)革新炉推進室長(併)原子力技術室長 宮下誠一 みやしたせいいち 廃炉産業室長(併) 横手広樹 よこてひろき 原子力立地・核燃料サイクル産業課長 皆川重治 みなかわしげはる 核燃料サイクル産業立地対策室長 勝見哲 かつみさとし 原子力立地政策室長(併)原子力広報室長 利根川雄大 とねがわゆうた 原子力政策企画調査官 山岸航 やまぎしわたる 放射性廃棄物対策課長(併)放射性廃棄物対策技術室長(併)放射性廃棄物対策広報室長 横手広樹 よこてひろき (併)放射性廃棄物対策広報室長 特許庁 特許庁長官 河西康之 かさいやすゆき 特許技監 安田太 やすだふとし 総務部(特許庁) 総務部長 吉澤隆 よしざわたかし 秘書課長 降井寮治 ふるいりょうじ 弁理士業務監理官 加藤智也 かとうともや 秘書課調査官 牧野信之 まきののぶゆき 総務課長 亀井明紀 かめいあきのり 業務管理企画官 原真一郎 はらしんいちろう 情報技術統括室長 上尾敬彦うえおたかひこ 会計課長 桑原靖雄 くわはらやすお 会計調査官 瓦吹雅彦 かわらぶきまさひこ 厚生管理官 三浦有紀 みうらゆき 企画調査課長 柳澤智也 やなぎさわともや 普及支援課長 吉野幸代 よしのさちよ 国際政策課長 武重竜男 たけしげたつお 国際制度企画官 新田亮 にったりょう 国際協力課長 新田稔 にったみのる 審査業務部(特許庁) 審査業務部長 師田晃彦 もろたあきひこ 審査業務課長 高橋憲夫 たかはしのりお 方式審査室長 門奈伸幸 もんなのぶゆき 登録室長 伊藤康雄 いとうやすお 出願課長 駒﨑利徳まざきとしのり 特許行政サービス室長 中山義弘かやまよしひろ 国際出願室長 杉山卓也 すぎやまたくや 国際意匠・商標出願室長 谷口雅之 たにぐちまさゆき 商標課長 根岸克弘 ねぎしかつひろ 審査第一部(特許庁) 審査第一部長 北村弘樹 きたむらひろき 調整課長 中野宏和 なかのひろかず 審査推進室長 髙橋克 たかはしまさる 審査基準室長 星野昌幸 ほしのまさゆき 意匠課長 久保田大輔 くぼただいすけ 審査第二部(特許庁) 審査第二部長 小松竜一 こまつりゅういち 審査第三部(特許庁) 審査第三部長 諸岡健一 もろおかけんいち 審査第四部(特許庁) 審査第四部長 仁科雅弘 にしなまさひろ 審判部(特許庁) 審判部長 野仲松男 のなかまつお 首席審判長 森藤淳志 もりふじあつし 審判課長 松下公一 まつしたこういち 審判書記官室長 西田拓也 にしだたくや 中小企業庁 中小企業庁長官 山下隆一 やましたりゅういち 次長 山本和徳 やまもとかずのり 長官官房(中小企業庁) 中小企業政策統括調整官 平泉洋 ひらいずみひろし 総務課長 黒田浩司 くろだひろし 企画調整室長 赤松寛明 あかまつよしあき 企画官(給付金制度管理担当)(併)訟務・債権管理室長 笛木知之 ふえきともゆき 企画官(給付金不正対応等担当) 大塚周平 おおつかしゅうへい 企画官(中小企業基盤整備機構担当) 市原克典 いちはらかつのり 中小企業政策企画調整官 鈴木望 すずきのぞみ 中小企業金融検査室長 橋本康司 はしもとこうじ 業務管理官 高橋隆 たかはしたかし 広報相談室長 木下宏一 きのしたひろかず デジタル・トランスフォーメーション企画調整官 平山毅 ひらやまつよし 事業環境部(中小企業庁) 事業環境部長 坂本里和 さかもとりわ 企画課長 佐伯徳彦 さえきのりひこ 調査室長 岡田直也 おかだなおや 事業環境地域分析室長(併) 岡田直也 おかだなおや 金融課長 橋本泰輔 はしもとたいすけ 企画官(資金供給・企業法制担当) 佐藤諒一 さとうりょういち 財務課長 笠井康広 かさいやすひろ 取引課長 小髙篤志 こだかあつし 統括官公需対策官 原健太郎 はらけんたろう 取引適正化調整官 小菅敦 こすげあつし 取引調査室長 杉山春男 すぎやまはるお 統括下請代金検査官 佐藤俊輔 さとうしゅんすけ 経営支援部(中小企業庁) 経営支援部長 山崎琢矢 やまざきたくや 経営支援課長 前田了 まえだりょう 経営力再構築伴走支援推進室長 二宮健晴 にのみやたけはる 海外展開支援室長 梅田英幸 うめだひでゆき 参事官(技術・経営革新担当)(併)技術・経営革新室長 森喜彦りよしひこ 生産性向上支援室長 山本慎一郎 やまもとしんいちろう 小規模企業振興課長 荒木太郎 あらきたろう 創業・新事業促進室長 大竹真貴 おおたけまさよし 経営安定対策室長 太刀川徹 たちかわとおる 商業課長 伊奈友子 いなともこ 中心市街地活性化室長(併) 伊奈友子 いなともこ 計量計測データバンク ニュースの窓-331-経済産業省 幹部名簿 2025年10月21日現在 計量計測データバンク ニュースの窓-303-経済産業省 幹部名簿 2025年7月7日現在 計量行政(METI/経済産業省) 計量制度見直し(METI/経済産業省) 自動捕捉式はかり 自動重量選別機、計量値付け機、質量ラベル貼付機を使用している事業者の皆様へ https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/flyer2.pdf() 令和9年4月からの使用制限(検定義務化)に向け令和7年度(2025年度)中の早期受検に御協力ください 令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。 受検期限直前の令和8年度に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和7年度中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。 よくいただく質問 「検定の対象となる自動捕捉式はかり」とは 目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の、 次のものが検定の対象となります。 なお、非自動はかりとして、定期検査済証印、検定証印等が付されたものは、自動はかりの検定対象外となります。 ○自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり) ○質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり) ○計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり) 「取引又は証明における計量に使用」とは 「取引」とは、「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、「証明」とは、 「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます。 「既に使用している自動捕捉式はかり」とは 令和6年(2024年)4月1日を基準日として、それよりも前から事業所等で、取引又は証明に おける計量に使用されていた「自動捕捉式はかり」をいいます。 指定検定機関及びその連絡先 現在、次の6事業者が自動捕捉式はかりの指定検定機関として指定されています。 検定のお申し込み先は、以下のとおり。 ㈱寺岡精工 / ㈱デジアイズ 03-3752-5601 https://www.teraokaseiko.com/jp/ support/verification/ 略号:TRK 大和製衡㈱ 078-918-6605 https://www.yamato-scale.co.jp/ support/verification/ 略号:YGV ㈱エー・アンド・デイ 048-593-1592 https://www.aandd.co.jp/support/ calibration/shiteikikan.html 略号:AND アンリツインフィビス㈱ 046-296-6585 https://www.anritsu.com/ja-jp/ anritsu-infivis/verification 略号:AIV 全国自動はかり検定㈱ 03-6758-5571 https://www.jcw-co.jp/ 略称/略号:JCW (一社)日本海事検定協会 045-271-8864 https://www.nkkk.or.jp/ hakarikentei/ 略号:NKK 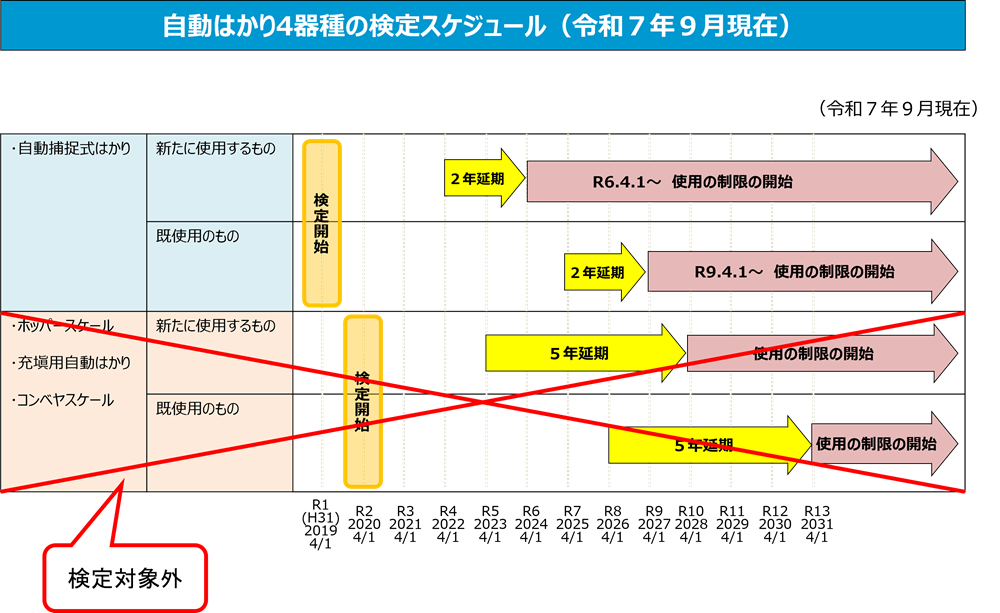 計量制度見直し 平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、①民間事業者の参入の促進 ②技術革新、社会的環境変化への対応 ③規制範囲・規定事項等の再整理・明確化を目的とし、平成29年より順次、計量法関係法令(計量法施行令、計量法施行規則等)を改正しています。 【更新履歴】 ・自動はかりのQ&A(令和7年9月版)(NEW!) ・自動はかりの検定制度の見直しについて(令和7年9月5日)(NEW!) ・指定検定機関の申請の考え方(第6版)を掲載しました (令和3年8月1日) ・指定検定機関の申請書類の手引(第3.2版)を掲載しました(令和3年8月1日) ・自動はかりの検定制度の見直しについて(令和3年8月1日) ・器差検定を中心とした指定検定機関を新たに指定しました(令和3年3月31日) 今までの更新履歴 自動はかりの検定制度の見直しについて 平成28年11月の計量行政審議会答申を踏まえた平成29年の政省令改正により導入することとされた自動はかりの検定制度について、 国内の自動はかりに関する実態を踏まえて、検定対象範囲や検定実施スケジュールなどについて見直しを行いました。 政省令改正の内容(平成29~令和4年度) 「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」の公布について(令和4年8月5日公布) 「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について(令和3年7月27日公布) 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成31年3月29日公布) 計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成31年3月25日公布) 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年9月6日公布) 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成30年3月30日公布) 計量法施行規則の一部を改正する省令等(平成29年9月22日公布) 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年6月21日公布) 関連資料 平成28年11月1日に計量行政審議会にて取りまとめられた答申を踏まえた計量制度の見直しの全般について概要を示した資料です。 計量制度の見直しについて <政省令改正にともなう自動はかりの検定実施> (令和元年6月版)(PDF形式:4,162KB)PDFファイル ※ 本資料は「自動はかりの検定制度の見直しについて」の反映前の内容となりますので、検定実施スケジュール等の最新情報については当ページ上部を御確認下さい。 自動はかり ①自動はかりとは 自動はかりとは、「計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかり」に該当するはかりのことを言います。 「操作者の介在」とは、単純な被計量物の載せ降ろしをする行為ではなく、内容量などが目的の設定量か否かの判断や、設定量に達するため常に手動で操作することなどを言います。 特定計量器に該当する自動はかりは取引又は証明に使用するか否かに関わらず、計量法施行令第2条に規定され「目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの」です(目量は各器種JISの「検査目量」に該当します)。 特定計量器に該当する自動はかりは、以下の5つに分類されます。 ・自動捕捉式はかり ・ホッパースケール ・充塡用自動はかり ・コンベヤスケール ・その他の自動はかり 詳細は、当該HPの「自動はかりのQ&A」や技術基準を定めるJISを参照ください。 ②自動はかりの5つの分類について 特定計量器に該当する自動はかりの概要は、以下の通りです。 各自動はかりの詳細は、当該HPの「自動はかりのQ&A」や技術基準を定めるJISを参照ください。 自動はかりの名称 技術基準 概要 自動捕捉式はかり JIS B7607:2024 自動捕捉式はかりとは「個別の物体の質量又はバラ状の物体の一塊の質量を計量する自動捕捉式はかり(自動重量選別機、質量ラベル貼付機及び計量値付け機の総称)」と規定される自動はかりのことを言います。 また、自動捕捉式はかりのうち、ひょう量が5kg以下のものが検定の対象になります。 ホッパースケール JIS B7603:2024 ホッパースケールとは「ホッパー形状の荷重受け部で、バルク製品(ばら荷の状態の製品)を分割計量し、再びバルク製品へ戻す自動はかり」と規定される自動はかりのことを言います。 ホッパースケールは、計量動作に応じて5つの呼称(不定量計量方式、正味量演算計量方式、定量計量方式、累積計量方式、総量計量方式)で分類されております。 充塡用自動はかり JIS B7604-1:2024 充塡用自動はかりとは「製品の個々の質量を自動計量して、所定質量ごとに充塡する自動はかりのうち、一定質量の製品を袋・容器(最終取引形態ではないタンクローリー,コンテナなどに充塡し,その後,製品を小分けにして再度充塡するものは除く。)に充塡することを意図したもので、供給装置・制御装置・排出装置を含むもの」と規定される自動はかりを言います。 コンベアスケール JIS B7606-1:2024 コンベヤスケールとは「搬送装置の動きを中断することなく、バルク(ばら荷)状態の製品の質量を、その製品に働く自由落下の加速度(重力)の作用とベルト速度との組合せによって連続計量するベルトコンベヤ型の自動はかりであって、単速度ベルトコンベヤ、可変速度ベルトコンベヤ又は他速度ベルトコンベヤとともに使用することを意図したもの」と規定される自動はかりを言います。 その他自動はかり - その他の自動はかりとは、4器種の自動はかり(自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベアスケール)以外の自動はかりのことを言います。また、4器種のそれぞれの定義から除外された自動はかりも該当します。 ただし、4器種に該当する以外のはかりにおいて、非自動はかりと判断されるものもある事にご留意ください。 ③技術基準 自動はかりの検定等に係る技術基準は、JISで規定することとしています。 自動捕捉式はかり [JIS B 7607] のJISが令和6年5月20日に公示されました。 充填用自動はかり [JIS B 7604-1] のJISが令和6年5月20日、[JIS B 7604-2]のJISが令和3年3月22日に公示されました。 ホッパースケール [JIS B 7603] のJISが令和6年5月20日に公示されました。 コンベヤースケール [JIS B 7606-1]のJISが令和6年5月20日、 [JIS B 7606-2]のJISが令和元年8月20日に公示されました。 下記のJISCのHPよりJIS検索画面で各JISについて番号を入力いただき、 該当する規格番号よりPDFにてご覧ください。※著作権保護のため、閲覧のみ可能となっています。 JIS検索(JISCサイトへ) ④自動はかりの4器種簡易判別フローチャート(令和4年8月版) 製造・修理している自動はかりが、自動はかりか否か、自動はかりである場合、ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール、自動捕捉式はかり、その他の自動はかりのどれに該当するか判断の参考にするための資料です。 自動はかりの4器種簡易判別フローチャート(令和4年8月版)(PDF形式:336KB)PDFファイル ⑤自動はかりにおける 「取引」/「証明」事例集 (平成29年12月版) 自動はかりを取引又は証明に使用している場合は自動はかりの検定が必要になりますが、お使いの自動はかりの使用方法が「取引」/「証明」に該当するかどうかを分類するための参考資料です。 自動はかりにおける 「取引」/「証明」事例集 (平成29年12月版)(PDF形式:803KB)PDFファイル ⑥自動はかりのQ&A(令和7年9月版) 自動はかりに関するよくある質問について、回答を作成しました。 自動はかりQ&A(令和7年9月版)(PDF形式:652KB)PDFファイル (New!) ※令和4年8月4日まで当該ページに記載されていた下記項目は、HP内「特定計量器を製造する場合」に移動しました。 ④自動はかりの製造事業者について(平成30年9月版) 器差検定を中心とした指定検定機関 自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定を行っております。 器差検定を中心に行う指定検定機関関連の情報は以下のリンクからご確認頂けます。 →指定検定機関関連情報 適正計量管理事業所 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)の規定に基づき、平成29年10月1日から、特定計量器である質量計に新たに「自動はかり」が追加されました。これに伴い、計量法第127条に基づく指定を受けている適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。 適正計量管理事業所関連の情報は以下のリンクからご確認頂けます。 →適正計量管理事業所関連情報 型式承認試験における試験成績書の受入れ 令和元年5月22日に、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第三十条の二第一項第二号の規定に基づき、型式の承認等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が認める国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関を公示いたしました。これに伴い、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)では、この公示にて認められた型式承認機関が発行する適合証明書を添付して行う型式承認の申請受入れを開始しています。 告示等の改廃履歴(令和元年5月22日) 型式承認試験(国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター)外部リンク また、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、型式承認制度に活用される試験所認定業務を開始しています。NITEから認定を受けた試験所が実施した非自動はかりの型式承認のための試験結果は、産総研への型式承認申請に活用でき、産総研で改めて試験を実施せずに当該試験結果を受け入れることが可能となります。 型式承認制度に活用される試験所認定の詳細は、NITE認定センターまでお問合せください。 認定センター(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク お問合せ先 イノベーション・環境局 計量行政室 お問合せの前に よくある質問と回答をご覧ください。 お問い合わせは、以下の問い合わせフォーム(メールによる問い合わせ)よりお願いいたします。 問合せフォームへ ※現在、多数の照会をいただいており、順番に対応させていただいております。 回答には1週間程度を見込んでおりますが、御質問の内容や照会の状況等により、 さらにお時間を要する事もございますので、予めご了承ください。 令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い 自動捕捉式はかり使用事業者 各位 経済産業省イノベーション・環境局計量行政室 令和7年8月22日 (https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/r7-soukijyukenn.pdf) 平素より、計量行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、計量法(平成4年法律第51号)において、昨年4月から、特定計量器に該当する自動捕捉式はかり(以下「自動捕捉式はかり」という。)のうち、新たに使用するものについての使用の制限(第16条)が開始され、検定が実施されている状況です。 既使用の自動捕捉式はかりについては、令和9年4月から使用の制限が開始されることとなっております。 自動捕捉式はかりの検定の有効期間は2年(適正計量管理事業所において使用する自動捕捉式はかりは6年)ですが、有効期間の始期は検定に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日となります。 そのため、令和8年度は、自動捕捉式はかりの検定業務を担う指定検定機関への検定依頼が集中することが予想されます。当該依頼が殺到した場合、指定検定機関における円滑な検定業務の実施に支障が生じ得るとともに、検定対象の自動捕捉式はかりを使用している事業者におかれましては、希望時期での受検が困難となり、想定以上に受検に期間を要することとなるおそれがあり、また、令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。 つきましては、検定対象の自動捕捉式はかりを使用している事業者におかれましては、可能な限り令和7年度中の早期受検に御協力いただきますようお願い申し上げます。 なお、自動捕捉式はかり、指定検定機関の詳細については、別紙を御参照ください。 【本件に関する問い合わせ先】 経済産業省 計量行政室 電 話:03-3501-1688(直通) メール:bzl-metrology-policy@meti.go.jp 【別紙】 1.検定の対象となる自動捕捉式はかり 目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、 ひょう量が5キログラム以下の、次のものが検定の対象となります。 なお、非自動はかりとして、定期検査済証印、検定証印等が付されたものは、自動はかりの検定対象外となります。 ○自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり) ○質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり) ○計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり 2.指定検定機関及びその連絡先 現在、次の6事業者が自動捕捉式はかりの指定検定機関として指定されています。 検定のお申し込み先は、以下のとおり。 〇株式会社寺岡精工、株式会社デジアイズ 03-3752-5601 https://www.teraokaseiko.com/jp/support/verification/ 〇大和製衡株式会社 078-918-6605 https://www.yamato-scale.co.jp/support/verification/ 〇株式会社エー・アンド・デイ 048-593-1592 https://www.aandd.co.jp/support/calibration/shiteikikan.html 〇アンリツインフィビス株式会社 046-296-6585 https://www.anritsu.com/ja-jp/anritsu-infivis/verification 〇全国自動はかり検定株式会社 03-6758-5571 https://www.jcw-co.jp/ 〇一般社団法人日本海事検定協会 045-271-8864 https://www.nkkk.or.jp/hakarikentei/ 金曜日の夜は紅葉と夕日と星空の八ヶ岳道路を走っていた。 先のことを決められるのは全てを知っている自分だけ [新刊図書紹介]「測定の不確かさとその周辺-不確かさの表現のガイド(GUM)をめぐる16のおはなし」榎原研正著、日本規格協会刊 高原の10月とミズナラの色付き 甲斐鐵太郎 [資料]メートル法の起源、キログラム史話、不滅のメートル法、追録版 アンリ・モロー(Henri Moreau)著 高田誠二訳 計量計測データバンク ニュースの窓-307-2025年のノーベル化学賞は京都大学の北川進特別教授、同ノーベル生理学・医学賞は大阪大学の坂口志文特任教授 日本人のノーベル賞受賞者 - Wikipedia 小梨の実が成る高原の秋 甲斐鐵太郎 質量の振る舞いを読み解く技術 [資料 ヒ素鑑定がらみの資料のweb記事] 1、砒素鑑定の計測値を100万倍して対数をプロットして同一であると見せかけた(指摘したのは河合潤京大教授) 2、和歌山毒カレー事件のことを調べておりました(計量計測データバンク編集部) 3、和歌山毒カレー事件とその真相(犯罪の証拠とされた砒素鑑定の成否を検証する資料集) 4、ヒ素鑑定の不正をあばいた河合潤氏 5、蛍光X線 - Wikipedia イギリス庭園と黄色い花 甲斐鐵太郎 ハカリの定期検査の実を上げる方策 花と色 その美しさは何のためにあるのか 甲斐鐵太郎 ヒッグス場と素粒子との相互作用が質量を生み出す(全ての力を説き明かす鍵)(計量計測データバンク編集部) (計量計測データバンク編集部) 計量検定所|沖縄県公式ホームページ 沖縄県 生活福祉部 計量検定所 〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町新川272-5 電話:098-889-2775 ファクス:098-889-1981 最新版業務概要 令和6年度版(令和5年度実績) 令和6年度業務概要 (PDF 2.5MB) 高山市の朝市2025 外国人旅行者で賑わう街 森夏之 計量制度への畏敬と矜持を表現する「指定定期検査機関推進宣言」 Word文章の一太郎ソフ変換、PDFの改行削除と空白を除去ツール 旅の宿 遠い世界とある思い出 森夏之 郡上おどり2025と長良川の水遊び 森夏之 中国の都市部マンション価格年収60倍が意味すること ある計測技術者外伝後日譚 ( 3 ) 矢野宏が関わった人物の逸話 矢野耕也 ある計測技術者外伝 後日譚(2) 戦争の記憶 矢野耕也 ある計測技術者外伝 後日譚(1) 計ると測る 矢野耕也 私の履歴書 安斎正一 目次 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その1-本欄の執筆をなぜ私が? 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その2-私の職場 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その3-私が生まれた日と父母兄弟について 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その4-夜間高校生と計量士との出会い 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その5-大学進学と空腹の日々 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その6-妻との出会い 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その7-寺岡精工へ入社 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その8-計量教習所と計量士資格取得 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その9-計量士資格取得 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その10-計量士会入会から役員35年間続く 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その11-寺岡精工CIは「新しい常識を創造する」 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その12-思い出に残る出来事 人命救助…お手柄少年安斎正一君 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その13-思い出に残る出来事 中学校の校長は「君は大きくなったら、偉い人になる」 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その14-私の内外の友 セブン銀行社長安斎隆氏は私と同郷、同級、同姓の仲 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その15-私の内外の友 アメリカ、マレーシア、オーストラリア、カナダ、香港に友あり 私の履歴書 安斎正一(計量士)-その16-思い出に残る出来事 米兵との出会いに思わず涙 夏至のころの瑞牆山(みずがきやま 標高2,230m) 森夏之 2025年度第1回 計量行政審議会 基本部会(METI/経済産業省) 2025年度第1回 計量行政審議会 基本部会 開催日 2025年4月25日 開催資料 議事次第(PDF形式:64KB)PDFファイル 資料1 自動はかり3器種の使用の制限の見直しについて(案)(PDF形式:1,530KB)PDFファイル 資料1(別紙) 計量法施行令新旧対照表(PDF形式:79KB)PDFファイル 資料2 検定有効期間等検討小委員会の設置について(案)(PDF形式:103KB)PDFファイル 参考資料1 計量行政審議会答申(平成28年11月1日)(PDF形式:1,794KB)PDFファイル 参考資料2 参照条文(PDF形式:131KB)PDFファイル 参考資料3 水道メーターの有効期間の変遷、現在の水道メーターの種類(PDF形式:431KB)PDFファイル 参考資料4 基本部会委員名簿(PDF形式:94KB)PDFファイル 議事要旨(PDF形式:135KB)PDFファイル 議事録(PDF形式:195KB)PDFファイル お問合せ先 イノベーション・環境局 基準認証政策課 計量行政室 電話:03-3501-1511(内線:3461) 最終更新日:2025年5月28日 令和7年度第1回計量行政審議会基本部会が令和7年4月25日(金)午後1時から同3時まで開かれた (計量計測データバンク ニュースの窓-298-) 中部7県計量協議会 2025年7月10日(木)に富山市のホテルグランテラス富山で会員.来賓など110名が参加して開かれ、協会事務運営体制整備と定期検査業務事務処理合理化方策を協議 経済産業省について 幹部名簿(最終更新日:2025年7月8日) https://www.meti.go.jp/intro/data/pdf/list_ja.pdf 経済産業省7月の人事異動に伴う幹部名簿は上記名簿が自動更新されます。 イノベーション・環境局 イノベーション・環境局長(併)首席スタートアップ創出推進政策統括調整官 菊川人吾 きくかわじんご 審議官(イノベーション・環境局担当)今村亘 いまむらわたる (中略) 計量行政室長 仁科 孝幸 にしな たかゆき 国際標準課長 中野 真吾 なかの しんご 国際標準化調整官 大出 真理子 おおで まりこ 国際電気標準課長 小太刀 慶明 こだち よしあき (以下略) 厚生労働省 幹部名簿(2025年7月8日付け) 「第13回質量測定に特化した不確かさWebセミナー」及び「第6回分銅校正技術Webセミナー」2025年10月21日(火)~22日(水)に開催 実施は不確かさセミナー事務局 特定計量器の届出製造事業者一覧(METI/経済産業省) 経済産業省指定製造事業者次の二社を指定 令和7年4月22日 391301 富士電機株式会社 東京工場 濃度計第一類 令和7年1月15日 022604 株式会社クボタ 精密機器事業ユニット 精密機器製造部 京都事業所 質量計第一類 指定製造事業者とは 世界経済を貿易の視点で眺める 貿易にかかわる一部基礎資料 世界の貿易輸出額ランキング - 世界経済のネタ帳 社会の統計と計量計測の統計(計量計測データバンク) ├「日本は貿易立国ではない]輸出依存度は15.2% 日本はもう貿易立国ではない。輸出依存型から内需依存型へ | セカイコネクトSTUDIO 中国の貿易収支・貿易輸出入額の推移 - 世界経済のネタ帳 貿易収支の推移 貿易輸出額の推移 貿易輸入額の推移 品質工学座談会 品質工学は計測技術にどう貢献したのか ―2014年座談会「品質工学は計測技術である」から10年を振り返って― 2024年10月5日開催(日本計量新報座談会) 品質工学の考え方 計量士 阿知波正之 飯塚幸三氏令和6年(2024年)10月26日逝去 伊勢崎賢治氏の話のなかにウクライナ紛争解決と戦争の本質理解の糸口が隠されている 伊勢崎賢治×神保哲生:NATOの「自分探し」とロシアのウクライナ軍事侵攻の関係 串田孫一 とうきょうFM「音楽の絵本」の録音版 モーツァルトの手紙から/串田孫一 音楽の絵本 「冬の記憶」 串田孫一 詩と朗読 計量計測トレーサビリティデータベースとその辞書 計量計測データバンク トップページ(計量計測データバンク目次) 日本計量新報全紙面 (PDFファイル)は「日本計量新報」本紙をご購読いただいている方のみ閲覧できます。 閲覧の際は、本紙に記載された「今月のIDとパスワード」を入力して下さい。
日本計量新報の全紙面閲覧(pdf版)のID&PWをご覧ください。
2025年11月のIDとPWは次のとおりです。 ID:5168 PW:N6HDA2K8 計量計測データバンク index 目次ページ(サイトマップ)
日本計量新報 週報デジタル版(2025年8 月7日までの重要ニュースと記事一覧) 日本計量新報 週報デジタル版(2025年8 月7日号から) 日本計量新報 週報デジタル版(2017年6月23日号から2025年7月31日号) 日本計量新報 電子版の全紙面のID&PW (日本計量新報は紙面をインターネットで閲覧することができます。 新聞と同じ形式のPDF ファイルです。webに掲載の全紙面です。どうぞご利用ください) (IDとPWは計量新報購読者に限り電子メールで月ごとにお知らせしております) 日本計量新報全紙面 (PDFファイル) 今月のIDとパスワードを入力して閲覧することができます。 日本計量新報の全紙面閲覧(pdf版)のID&PWをご覧ください。 2025年11月のIDとPWは次のとおりです。 ID:5168 PW:N6HDA2K8 株式会社計量計測データバンク 編集部 edit@keiryou-keisoku.co.jp 〒136-0071 東京都江東区亀戸7丁目62-16-803 電話番号03-5628-7070 FAX03-5628-7071 日本計量新報あて電子メール mail@keiryou-keisoku.co.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計量計測データバンク 気になる重要情報 ニュースや科学・文化欄などの記事にする予定の資料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会の統計と計量計測の統計【分類13】日本の計量法と計量関係法規 |