├
├計量計測データバンク ニュースの窓-189-太平洋戦争、開戦と終結の諸事情(2)
├
├
├
├
├
├
├官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介
├
├福島新吾―体験戦後史 1945~47―旧制一高、東大法学部、学徒出陣、東大社会科学研究所助手時
ポツダム宣言受諾へ
-人事課長に大学を卒業すれば高等官へ推薦の道もあるといわれ試験もなしに大学生のまま嘱託に採用される-
母方の祖父と伯父が共に外交官だったからかねてその道を目指していた。しかし大学授業短縮で昭和18年春の最後の高等文官試験(外交科)を受 けられず兵役に服したので、高等官になれない。それは承知でせめて外務省で働きたいと思った。成田人事課長に大学を卒業すれば高等官へ推薦の道もあるといわれ、試験もなしに大学生のまま嘱託に採用され、世田谷区下馬の分室勤務を命じられた。兄の1942年秋の初任給も5~60円だった。しかし戦時インフレで、会計課が斡旋したヤミ鯨肉2キロを買ったら最初の月給は無くなったと記憶する。
1945年5月の空襲で東京霞が関の外務省庁舎は罹災した。焼け跡を囲む古典的な飾りのついた鉄柵ばかりが残って哀れであった。その前に外務省調査局は、今の東急東横線学芸大学駅に近い、当時の東京第一 師範(学徒勤労動員で休校状態だったと思う。現在の東京学芸大付属高校)に分室として移転していた。本省はどこに移ったのか知らない。8月の11日か12日、その一室で、隣の課の課長がいつもより多い四、五人の課員を集めて「まだ秘密だが、ポツダム宣言の受諾がきまって連合国と接触中だ」と伝え、破顔一笑「助かった。これで私の家は焼けないですんだ」とつぶやいた。私はかねて課内で読んでいた外国公館からの秘密電報の内容などから、近くこんな結末になろうとはおよそ承知していたから、事柄には驚きはしなかった。しかし国家の重大事に対するこの課長のあまりにも私的な受け止め方に心から腹を立てた。
-無人の部屋で暇にあかして棚から勝手に機密電報を引っ張り出し、片っ端から拾い読み-中立国を介しての米英政府への必死の和平のための接触(外国電報ではpeace-feelersといわれていた)
私の勤務なるものは、通常はほとんど無人の部屋で、暇にあかして棚から勝手に機密電報を引っ張り出し、片っ端から拾い読みをすることにつきた。そこには大本営発表とは正反対に、珊瑚海、フィリピン沖海戦の大敗、「陸奥」「武蔵」「信濃」「大和」など大艦の無為の撃沈や事故、スイス、スウェーデンなど駐在の日本の外交官たちの報告(アイルランドのダブリン駐在の別府節弥領事のものが特にすぐれていた)。中立国を介しての米英政府への必死の和平のための接触(外国電報ではpeace-feelersといわれていた)、佐藤尚武駐ソ大使以下の、(和平斡旋依頼のための)近衛特使のソ連派遣受入れ交渉の顛末などが記され、眼から鱗の落ちる思いを日々くりかえしていた。
佐藤尚武駐ソ大使公電に報じられた1945年度ソ連国家予算の分析(私の結論はソ連は対独戦は終わるのに国防費を減額 していない。対日戦に要注意ということ)
戦争末期の外務省調査局には実は何の仕事もない。人事課の乙津領事は上海で幼い私を覚えていると言われたが、課長の吉田氏は欠勤。かわりの上司にあたる課付きの市川泰治郎元シドニー領事から二三の調査を命じられた。佐藤尚武駐ソ大使公電に報じられた1945年度ソ連国家予算の分析(私の結論はソ連は対独戦は終わるのに国防費を減額 していない。佐藤尚武 - Wikipedia.。対日戦に要注意ということ)。又当時まだクーリエ(傳書使、courrier)が駐 ソその他中立国大使館から運搬していた"DailyWorker"のレジュメが求められた。
米国の株式価格変動を太平洋の戦局(フィリピン、沖縄、硫黄島など)と対比してグラフに取ってみた。株価の上下には全く勝敗の影響が見られず、もはや戦争の大勢は決しているとの判断がついた
今思うに外務省としてそんな将来的ビジョンなどなかっただろうから、彼の個人的に興味のあるものを小手調べにやらせて見たのだろう。レジュメの意味が分からず、問い返したら、作ったことがないのかとやや軽蔑気味に説明されて屈辱を覚えた。マスプロ教育 の東大と昭和初期の東京商大の違いだった。古くから基礎的研究が重んじられた商大ではそんなゼミ教育が行われていたのだろう。東大ではそうした経験を持てなかった。それによって女性たちに、新聞を何時まで読んでいるのと馬鹿にされながら、世界労働組合会議創立総会の概要を作った。さらに世界労連の決議に戦争犯罪人の処罰要求があったので、第一次大戦の戦争犯罪人処罰の実態をアメリカの政治学雑誌で調べた。そしてカイザーはオランダに亡命したので、処罰できず、戦時国際法違反者の処分に終わったと報告した。今一つ自分で考えついて当時『中外商業新報』といったか、『日本産業経済新聞』だったかに掲載されていた米国の株式価格変動を太平洋の戦局(フィリピン、沖縄、硫黄島など)と対比してグラフに取ってみた。株価の上下には全く勝敗の影響が見られず、もはや戦争の大勢は決しているとの判断がついた。
市川氏はそれを見せても口を閉ざしたままで何も感想はもらさなかった。そんなことは多分識者にはすでに当然だったし、憲兵の耳を警戒する面もあったのだろう。当時日本の自然科学者たちが、日本の数字の単位は四桁刻みだから、西洋式に三桁でコ ンマを入れず、四桁にすべ と提案していたのに同調して、数字を四桁に刻んだら、帰国子女のタイピス トが不思議がった。
幸い勤務開始のころまでで東京の大空襲は終わっていたから、宿直の夜に空襲警報は出なかった
ほかには、週一回くらいの防空用の宿直勤務が主な負担だったと記憶する。幸い勤務開始のころまでで東京の大空襲は終わっていたから、宿直の夜に空襲警報は出なかったが、警戒警報下で暗いビルを孤立した二、三人で警備しているのは不安であった。当時問題 の課長など欠勤続きで、市川氏なども空襲にかまけてさっぱり出勤しない。前の机の乾末松嘱託も私の幼年時代に上海で父と面識が有った人だったが、対面しないうちに空襲で焼死し連絡は途絶えたままであった。その机上に残 置されたStatesman'sYearBookなどの参考資料を私がそっくり引き継いで利用した。
そんな状態で勤務中に会話する相手は殆どなかったが、それでも出勤している人は分室全体ではかなりの人数で帰途何人かの同僚と歩きながら短時間でも話すことは楽しみであった。なかに戦前に米国国会図書館日本課長を勤めていて戦時下に交換船で帰国した坂西志保女史(1896~1976、戦後国家公安委員)がいた。
四月からローズベルトに代わって大統領に昇格したトルーマンは"ローズベルトがratherleftだったのと違ってratherrightinthecenter"だと説明してくれて、そういう分類をするものかとそのrの発音と共に感心した記憶がある。
隣の調査局第二課には罹災者に支給された兵隊服を着て肩から雑嚢をかけたやや背の高いロイド眼鏡の人物がいた。これが後に社会科学研究所の教授として再会し、思想的な指導をも受けたソ連法専攻の山之内一郎氏だった。また伯父の隣家にいた伊藤嬢は三軒茶屋から玉川電車に乗るまで帰途が同じでよく会話を楽しんだ。戦争への危機感も一致した。戦後思い出して訪ねたらすでに結婚して不在であった。岡本達郎君という青年は戦後占領軍に勤めていて、再会したことがあった。
私の勤務なるものは、通常はほとんど無人の部屋で、暇にあかして棚から勝手に機密電報を引っ張り出し、片っ端から拾い読みをすることにつきた。そこには大本営発表とは正反対に、珊瑚海、フィリピン沖海戦の大敗、「陸奥」「武蔵」「信濃」「大和」など大艦の無為の撃沈や事故、スイス、スウェーデンなど駐在の日本の外交官たちの報告(アイルランドのダブリン駐在の別府節弥領事のものが特にすぐれていた)。中立国を介しての米英政府への必死の和平のための接触(外国電報ではpeace-feelersといわれていた)、佐藤尚武駐ソ大使以下の、(和平斡旋依頼のための)近衛特使のソ連派遣受入れ交渉の顛末などが記され、眼から鱗の落ちる思いを日々くりかえしていた。
あきれた事にある日、出仕早々の嘱託の私に、誰も出勤していないから課長会議へ出ろと呼び出しがかかった。多分ほとんど代理ばかりの十人たらずの会議であったが、その議題は東京も危なくなって、もはやこれ以上分室を残置するのは無理だろう。再疎開を考えるなら何処が良いかという話。そして議長の渋沢調査局長は何と未だ食糧のありそうな伊豆半島はどうかという。当時岩手県の宮古や房総ではすでに激しい艦砲射撃を受け敵の本土上陸は近いと予想されていた。九十九里浜か、相模湾が上陸地点と見られたのに、いくら何でもそこに近い危険な所をめざすとはとその非常識に唖然とした。しかしその後報告すべき上司とあわぬうちに私が赤痢にかかって約三週間欠勤してその会議は聞きはなしに終わった。
これより先二月に、東大法学部研究室にゼミナール指導の国際法の安井郁教授に復員の挨拶をした。その時安井さんは「もう日本には近代戦を遂行する戦力は無い、南原(繁、政治学史、後の東大総長)、高木(八尺、米国政治史)両教授などが講和のために奔走されている。日ソ中立条約もサンフランシスコ会議後、廃棄は必至だ。最高政策の断が必要だ」と私に語った。当時小磯内閣は公にはまだ焦土抗戦を唱えていたから、実は降伏は間近いのかと愕然とした。帰宅して母や戦傷で召集解除巾だった兄にその話を伝 え、政府の無力を嘆きあったものだ。その頃東京は数回の小規模な爆撃、焼夷攻撃を受 け、人は疎開に血眼で古道具や古本はタダ同然に山のように店に出ていた。戦争終結に賭ける投機感覚と資金があったら、東京の土地を買い占めることも可能だったかなと思うほどだ。
ソ連の講和仲介に密かに期待を寄せたりしていた
明日を知らぬ身にもこれらの文章は読んでそのまま血肉になるような思いがした。死を前にしての諦観だろうか。また父の蔵書にあった北一輝『国家改造法案大綱』などを読み、ソ連の講和仲介に密かに期待を寄せたりしていた。はずかしいが当時のあきれるばかりの国家主義、軍国主義への傾倒ぶりを日記の一部を抄録して告白しておこう。
「四月二十八日 ベルリンは完全に包囲もされ市内も制圧されてしまって、全く最後の運命に晒された。ドイツに残る山岳ゲリラの手は果たしどの程度に有効か。日本への全面的攻勢の日は近い。死闘の用意を急がねば。」山岳ゲリラなどどこで聞いたのか。
八月九日(木)ついにソ連開戦せり ポッダム会談にあんまりスターリンの言い分が通り過ぎる
八月九日(木)。ついにソ連開戦せり。今の世界には道義などかけらほどもない。国際法の躁躇が如何に堂々と行われることか。MachtPolitikのみ。如何にして日本はその永遠の生命を守るべきか。危機なる哉。ソ連の出方は意外に早かったなあ。どうもポッダム会談にあんまりスターリンの言い分が通り過ぎると思った。
戦時の日記はこれが最後でその後の破局の日記はない。この数日後に初めに書いた課長の降伏予告があったはずだ。
八・一五の玉音放送は、隣組の焼け出された人々がラジオを持たなかったから、我が家に大勢集めて正座で畏まって聞いた。音声は明瞭で、予告もあったから降伏はハッキリ理解した。涙は止まらなかった。省みて政府の戦争方針も不徹底だったし、自分自身も優柔不断で、戦争努力に完全燃焼しきれなかったという悔しさが強かった。同時に初めて聞 く天皇の発音とアクセントの異様さには驚きと幻滅を感じた。
その日の新聞が午後には配られたのだったろうか。そこに敗戦にいたる戦闘の経過が初めて公表されていた。それを食いいるように読んで、嘘を並べてきた軍部に憤りを感じた。
近くの陸軍の経理の将官が軍用物資を山のようにトラックで持ちかえった
八月末になって一年前に戦病死した戦友故佐久問豊実君の父君を船橋に弔問した。中学校長だったという謹厳な父親は、近くの陸軍の経理の将官が軍用物資を山のようにトラックで持ちかえったと身をふるわせて憤っていた。その痛烈な軍部批判に、観念的な愛国主義者は反省させられることが多かった。
降伏の数日後、命じられて膨大な数の「機密文書」の山を焼いていた
降伏の数日後、私は第一師範の校庭に掘った大きな穴に、命じられた膨大な数の「機密文書」の山を次々に投げ込んでは焼き捨てていた。その大部分は戦時中最後まで中立国だった、スウェーデン、アイルランド、スイスなどに残留した日本外交公館が西欧の新聞雑誌などから入手した敵国側の情報を、本省あてに送ってきた暗号電報の解読であった。
それらは暗号解読の素材になる〔戦争終結後に?〕以外は、戦時中に一般国民や憲兵に対して極秘であっただけで、米国に対して何も秘密な事などなかったのだから、焼却する必要があったかどうか疑わしい。
その多くは未だ読んでいなかったから、敗戦後でもそこに何が書かれていたのか好奇心があり、何とか焼かずに保管できないものかなあと思いながら、紅蓮の炎に空襲の業火を重ね合わせて見守っていた。
「これから日本はどうするのでしょう?」という私の質問に、かって中国に在勤した年長の同僚の属官は「支那では役人も市民もみんなが昼と夜と二重の仕事でかせいで食いつないでいたのさ。日本もそうなる。」と答えた。
幼時に上海でさんざん眺めた、あらゆる町角にあふれる、ボロに包まれたクーリー(苦 力、下層労働者)や、乞食、カッパライとバクチで食いつなぐ浮浪児の姿が眼に浮かんだ。かって農村崩壊を憂いて決起した』二・二六の青年将校達の思想を思い起こすと「戦争で何一つ問題は解決していないではないか!」と悔やまれるのであった。
いよいよ敵の第一次進駐は明後日〔台風で二十八日に延期〕厚木に行われる
戦後最初の日記。「八月二十四日(金)。大詔を拝して丸十日、どうやら外地各戦線とも停戦は実行された様子。いよいよ敵の第一次進駐は明後日〔台風で二十八日に延期〕厚木に行われ、明日からは敵の監視飛行が始まって日の丸の飛行機の飛ぶのを見るのは今日を限りとなる。
この十日の心の動きを振り返ると実に複雑なものがある。しかもその中から何等行動の指針が る かみ得なかったところに俺の今の最大の欠点たる無気力が表れている。大詔を拝した瞬間は事をここに至らしめた国民の罪を痛感し陛下にこれほどまでの御言葉を告(の)らせ給うの止むなきに至らしめた輔弼(ほひつ)の臣の無為無策を痛憤した。陛下がこの戦争中国民はその全力を尽くしたとねぎらい給うた時ほど恥ずかしく、嘘だと絶叫したかった事はない。しかも時を経るにつれ、ますます重臣たちが反戦的に策動したという印象が強く戦力が未だ尽きざるに[何と認識が不正確なことだろう!]手をあげる事の『意地』の上からの口惜しさも手伝い、反停戦の暗殺等の噂をきくと、何とか大勢をひっくりかえしてくれぬかとの希望をすら抱いた。
しかし一方東久遍宮の御放送をきくと純粋に大詔を奉戴し再建に努力すべきだとの気持ちも沸き他方、一般人の米占領軍に対する不安についてはどうもそれほど組織的に乱暴は行いそうもないと思うところからやたらに停戦協定に違反する事も考えもの(どうせ再交戦 は不可能なのだから)という気もして両者の矛盾に苦しんだ。」未だ天皇主義にひたりき っていた若者だが、早くも転換の煩悶が始まっていた。天皇が皇室存続のためのみをはかって講和を決断した経過を全く理解していない。
そこに様々の指示と戦時中の指針との矛盾が出ていることに迷わされていたのである。
占領支配
多分9月2日の戦艦「ミゾリー」号艦上での降伏文書調印式の当日、私は港区田村町の元の日産ビル(当時は満州重工業を作った日産コンツェルンとして有名)にあった終戦連絡事務局(8月26日に占領軍と日本政府との連絡のために外務省の外局として新設された)に出向しており、電力不足で昼も薄暗い大きな事務室の一角で、配られた「指令(名前は不正確かも)第1号」「第2号」の綴りに驚いていた。「第2号」は戦犯逮捕の指令であった。
それはポッダム宣言から予期され、私も終戦前に第一次大戦後のドイツの戦犯の処理 を調査したりしていた。
だがその多数の人名の列挙を一見してすぐ頭山満や中野正剛など多くの死亡者、またとても戦犯には当たらない政治的に無力な人物を見た。「何だ。米軍の情報はこの程度か」との軽侮と、戦時中少ない情報で外国政治家の人名録なども印刷配付していた同盟通信のレベルは低くはなかったなと自負の念も起こった。
後に刊行された『日本管理法令研究』(1946年5月)には「指令第2号」(9月3日)は連合国最高司令官の管理すべき地域の降伏その他占領に関する手続きを定めたものであり、戦犯逮捕を命じた指令はない。実際には戦犯一括のリストは公表されず、9月11日東条英機以下36人、12月2日広田弘毅以下59人、同6日近衛、木戸以下9人となしくずしに、およそ100人がA級戦犯として米軍MPにより直接逮捕されたと思う。
そのA級戦犯の人数や氏名も私の記憶の最初の指定とは大きく違っていた。多分この文書は一旦取り消されたのだろう。その後B、C級の戦犯は千人をこえたが、その文書では政治家、軍人、経済人、思想家などの有名人ばかりでB、C級は含まれていなかった。
--現存の日本政府機構を利用するが、それを支持するものではない。」としていた--(から、正式には間接統治は変えなかった)
第1号の方はもっと重大な占領軍の日本直接統治の指令であった。ポツダム宣言で日本は間接統治とされているのにと愕然とした、これは米軍当局者の無知か、連合国の欺隔 か。外務当局の上層部はこれに直ちに抗議しているのだろうかと焦りを覚えた記憶がある。
『管理法令』では「指令第1号」(9月2日)は 「一・般 命令第1号 、陸海軍」(軍 隊が降伏する諸手続きを定めたもの)を発布する命令を中心にした簡単なものである。だが、私の見たものは、9月10日にワシントンで発表した「日本管理方針」に似たものだった。9月22日に日本で発表された「降伏後に於ける米国の初期の対日方針」の第二部第二節には「現存の日本政府機構を利用するが、それを支持するものではない。」としていたから、正式には間接統治は変えなかったわけだ。
この直接統治の文書の記憶について私はずっと幻を抱いていたような気がしていた。この点を「占領史研究会」(後に解散)の天川晃(横浜国大教授)、袖井林二郎(法政大教授)両氏に質問したら、やはり降伏当初Proclamations(布告)というものが二、三発せられ、重光外相が交渉して撤回した経緯があったとその頃分かったらしい。戦犯リストも米軍に準備がなく、フィリピン米軍の参謀部であわててズサンなものをでっち上げたことがあったとサザーランド準将のメモワールにあるそうだ。
私の記憶は幻ではなかった。何しろ米軍が進駐を開始した直後の8月30日一日だけで、私が見た終連横浜支局からの通報では神奈川県下の米兵の強盗、せっ盗、婦女暴行は千件をこえていた。それは戦時中の宣伝の「鬼畜米英」のイメージそのままであった。
数日でこの種の報告は禁止された。新聞ではしばらく「黒い大男の犯行」などと表現 していたが、やがてそれも許されなくなった。
個人的な事例だが我が家で戦前5メートル級中古ヨットを一隻逗子の鐙摺漁港に所有していた。それが米兵のために見苦しいと一方的に焼き捨てられてしまった ことをずっと後になって知ったが、何処にも訴えようがなかった。
そんな時代であったから、この情報にふれて、ひょっとすると米軍は本気で直接統治 するのかもしれないと不安になった。
その指令?の中に「日本政府の官吏の辞職は一切認めない」という項目もあった。「我 々も止められないのでしょうか?」と慌てて上司に聞いてみたら、「下っ端は問題にならんよ」と一蹴された。
しかし外交官庁から占領軍のメッセンジャーボーイに転落した終戦連絡事務局で、属官はさらに高文を通った事務官の使い走りであった。一つの文書に多くの課長や部長のメ クラ判をおしてもらう稟議書(りんぎしょ)を持ち回らされて馬鹿々々しくなった。しか もその事務官たちの知的常識の低いことにまたまた呆れさせられた。
米軍が二十四時間制の文書をよこすのに、十五時と書かれていると午後五時と読み違える始末だった。
高等文官試験を戦前にパスしていない身でこんな連中に一生使われたのではとても我慢が出来ないと感じた。
多分それらが退職を決意させたのだろう。辞令は9月18日付けである。
戦後の再出発・復学
その後のソ連による東欧の占領政策を知ると、ソ連にではなく米国に占領された ことは不幸中の幸せだったと認めるのが公平かも知れない。
戦災を受けた安倍先生は世田谷の私の家の近所に仮寓しておられ、46年1月から5月までは幣原内閣の文相を勤めた。母が安倍恭子夫人(藤村操の妹)と東京府立第二高等女学校同級の親友だったので、入閣前から何度かたずねて先生の話を聞く機会があった。十畳位の一間に僅かな食器、日常家具と布団などを積み上げて、夫妻で起居されていた。その不便な暮らしの中で、『今ラジオで「夏の夜の夢」のオペラを聴いていた。面白いね』などと悠々たるものだった。
宗教とは何かと問うと『個人の命を宇宙の大生命とつらねるものだ』といわれたが宗教 に入らなかったのは何故とたずねる機会はもたなかった。また当時の米国教育使節団と学制改革について論じあい、旧制高等学校の長所を力説しその存続を求めたが受け入れ られなかったとこぼされたこともあった。
アイケルバーガー中将が帰国する時には、貨物船一杯日本の骨董などを持ちかえった と非難されていた。
私は多分9月中旬東京帝国大学(まだこの名前であった)法学部に復学した。学徒出陣にあたり文部省は昭和18年9月に二年修了(とい っても戦時の学年短縮で、最初の半年で一年の講義を終了したから、実質は入学後一年半だった)の学生にはある程度の単位取得をしていれば「仮卒業」という資格を与え、在学のまま翌19年9月に卒業させることに した。
そこで同期生はほとんど仮卒業になっている。(銀杏会調べによると政治学科407法律学科87計494名である。入学は約800だったはず)。 私も仮卒業資格があったが、当時まだ三年配当科目など七科目を残しており、「戦死するなら大学生のままでいたい。生きて帰れば、しっかり受講したい」という論理で、仮卒業の申請をしなかった。そこで敗戦後のこの時仮卒業組は聴講生にされたが、私は復学が出来た。とはいえ食糧危機、インフレ、交通機関の崩壊の中で、結核を患った身には殺人的混雑の電車で通学し、肋骨が折れる危険を冒すのは容易ではなかった。
母と兄弟たちとは食糧は不足しても、久し振りに一家団樂の夕食が持てた。戦没者を家族から出さなかった幸運に恵まれた暖かさであった。毎夜のように停電が続く中で、蝋燭をたよりに、数個の数の足りない蜜柑をジャンケンで取り合いをして笑いころげたこと等、今の人には分からない平和の喜びでなっかしい思い出である。家族一同でホームソングや当時流行りだした「りんごの唄」などの斉唱を楽しんだ時もあった。
昼間学校に出て友人を見つけて、やっと民主主義、社会主義、軍国主義などと議論に熱を上げる時にすぎなかったが意外に充実した日々だった。東大の御殿下と呼ばれたグランドの前の芝生に、復員服を来た一高文科丙類(フランス語を第一外国語とした)同級の友人たちが、日を追って帰ってきて、再会を喜び合った。
米兵に大和撫子を躁躇されていると敗戦日本を悲憤する者、沖縄戦で敗走して必死にな って豚小屋にもぐり、泥まみれになって生き延びたいきさつを自ら戯画化して語る友、二度も南海に撃沈されて水泳部の実力を発揮して救われた勇士の話などなど鮮烈に記憶する。
人間魚雷「回天」の乗組になって、出撃しては故障で生き残った中学の日頃おとなしい友人の話も噂に聞いて襟を正した。
講義に出てみると戦前と同じ教授のいうことがまるで変わっており、それに反発を感じる場合もあった。それは多分川島武宜先生だ っただろう。名著『所有権法の理論』を戦時中にまとめた川島さんは、私達のクラスに物権法の特別講義をして、ゲヴェーレなどという難しい概念を教えて悩ましたが、「私はマルクス主義者ではありませんが」とわさわざことわっておずおずとマルクスの説を一部紹介していた。それが今や公然 とマルクス曰くとやっていたからだ。それが悪いわけではいのだが、転換があまり際立ってお り、大阪高校同窓の安井さんに似たキザな印象があって感情的に反発したのだろう。
他方丸山真男先生(まだ『世界』の論文を発表して強烈な反響を呼ぶ前)や 、一高で教えを受けた大塚久雄先生(戦時中東大講師)の講義を何度か聞けたことがよかった。また多分大河内先生あたりから史的唯物論の壮大な構想を聞くことができて、世界観が変わる思いをした。
末弘先生の労働法もようやく禁止が解け、時代の焦点となり興味は深かった。南原先生は一度位しか聞けなか った。たまにしか講義に出ず、戦前のようにノー トの空白を埋めさせてくれる友もなく参考書も入手できず、うぶなことに空手で受験する勇気が無かったので試験は放棄続きで、卒業のメドがたたなかった。
大学側は溢れている学生を早く卒業させたがっていたので、早く相談すればよかったのだが、窓口の指導を受けてみたら敗戦から一年半たった1947年3月になっても戦時の特典があり、既得単位だけで不足があっても卒業出来た。
こうして中途半端な「仮卒業拒否」は消えた。結局私は卒業年度をおくらせ生涯給与 の号数で損をしたが、この一年半の間のわずかな聴講で戦後の教授たちの自由な講義を耳にしたことが私に大きな思想的変化を与えた。そのために同期で戦後に大学の講義を聞かなかった仮卒業組とは生涯長く政治的、社会的な意見が違う思いをした。
10月頃、アダム・スミス『国富論』の輪読を友人と二人で始めた。敗戦後の経済大混乱を理解すべく手をつけたが、戦争中の空白は大きく英語の読解力もさることながら、経済史の細部に至るまで知らないことだらけだった。戦時中よみかけて、空襲以後中絶していた大塚久雄先生の『近代欧州経済史序説』をまた読み始めていたので、その注にならって、父が米国から持っていた"Palgrave'sDictionaryofPoliticalEconomy"を引いて一々未知の概念や史実を調べた。これは自分にはとても面白い勉強だったのだが遅々として読み進まず、戦後の日本経済の現状を知るための研究とはとうてい対応しなかったわけで友人をうん ざりさせた。
このころのノー トに、「十 月十六 日、p28.c.1.今 日の如 く貨幣 価値 が下 が る と人 はquantityofmoney(貨幣量)で 考 え ることを止 めvalueofuse(使 用価値)を 考 える。或 いはquantityoflabour(労働量)を考える。
私も独力では読み続けられず、卒業見込みのたたないまま、転地先の父との連絡、銀行の当座貸越口座からの戦時中の借越返済対策、母の手伝い、家庭の菜園係などをあたふたと続けることになった。
(大局の把握不足)冷静に判断したところでは、日本が支那事変に移行した時、初めは北支の特殊行政区域化をはか った方針に於いて明らかに攻撃的であり、少くとも今唱える如き対等の友好関係を求める方針ではなかった。満州国建設的な行き方であり、将来大いに努力して楽土と化して初めて正当化する困難な路であった。それが間もなく支那全面に及び、更に注政権支持にかわり、それが更に対等日支国交へ大転換した。この日米国交調整をやるにあたり大陸全面撤兵の譲歩は今から考えれば出来ぬことではなかったのである。しかるに当初の特殊化的考えにこだわってとても出来ぬように考えたのは軍部の考え方に動かされたのであろう。
(現実認識の甘さ)更に昭南、ジャワ、スマトラまで占領するや一応楽観的になり、その時終戦の形式として流石に宣伝の如きN.Y.占領と云う夢物語には同意しなかったにしろ直ぐその時を講和の最適期と考えず、一応内線の防備に成功し、敵が防衛線突破作戦に倦んだ時こそ妥協の時であり、その時も南洋圏の確保が出来ると云うが如き甘い考え方をしていたのも流された証拠だ。
父の生涯
①苦学の人。喜三次(きそうじ、伝にきさじとあるのは誤り)は福島喜平の第七子、五男。
父は、小学校(尋常科四年、高等科四年)を優秀な成績で卒業すると、郷土の有力者の学資援助により、1900(明治33)年3月28日校長若杉米太郎から第1号の卒業証書を受けて長崎商業を卒業した。さらに佐賀出身の元代議士松尾寛三(天草電灯社長、勧銀監査役、深川製磁監査役)の書生となって同年秋東京高商に入学した。
同期には後の佐藤尚武外相(1882~1971、当時田中姓)、小坂順造信越化学社長(1881~1960)、向井忠晴三井合名理事長・蔵相(1885~1982、雅楽の名門多忠久の長男、二歳で向井忠二郎の養子。飛級で開成中学を経て東京高商に15歳で進学した(追想録『向井忠晴』1986)などがいた。
在学中1902(明治35)年には佐藤、小坂らとともに一橋会と名付けた学生会創立委員の一人となっている(東京商科大学一橋会発行『一橋五十年史』)。当時から英語会で活躍していたようで、ボート部でも選手となった。
苦学ながら明治37年の官報によると144名中の首席で卒業。校費で中国の漢口まで旅行させてもらったという。
②長い在米経験。
ついで向井らと三井物産に入社(前 記向井追想録に三井物産入社十人の写真があり、福島は前列中央に向井は後列にいる。すべて東京高商卒だろうか?。向井は別のところで「戦争景気で …… 同級生だけでも四十九人も入りました」と述べている。三井物産編『回顧録』。)、門司勤務(1905.2月雑品係、日露戦争中に学業で徴兵を免除されていた身なので有田に帰るとっかまるということで、母が門司まで逢いに来た)の後同年8月5日ニューヨーク支店、翌年8月同勘定係に転出した。当時ニューヨークで日本料理店に二十八人の日本人社員が集まった写真がある。三井の発展ぶりに驚かされる。次いで1906年からオクラホマ、ヒューストンなどを経て1912年ダラス出張所長。以後1920年まで勤務し、綿花の買い付けを中心に15年在米した。1913年には32才で三井物産の現地法人(1911年からつくられていた)Southem ProductsCo.(後SouthemCottonCo.)の社長になっている。そして第一次大戦になると米綿が暴落したが、長期的戦略で買い付け、 欧州向け貨物船も先物を大幅に予約したが、その後貨物船の需要が激増し大当たりに当たって、…挙に大手の米国綿花商に頭をさげさせ る世界一流の綿花商になった。
ところが大戦末期には見通し悪く、欧州向けの飛行機までを含む多額の軍需物資を買い付けたところで休戦となり、綿花も大暴落をして当時の金額で400万円(1986年の金で100億円)の損失を出す結末で本社に召還された(『トーメン社内報、昭和56年5・6月』東島健児、『同'86.9.10』浮村専務)。それは当時の本店綿花部長児玉一造の強い支持の下に行われたのであったが、幹部の安川雄之助らの批判で、三井が綿花部を独立させて東洋綿花を設立した(社長児玉一造)きっかけにもなり、この悪印象が父の三井生活で終生深い傷となったようだ。
この長い在米期間(帰国は結婚とその後の二度だけ)に大学も一時聴講し、英語も熟達 し、日本人で初めてダラスロータリー・クラブに入会した。訪米した三井銀行の米山梅吉もこれに強い関心を持った。福島は帰国にあたりクラブの日本での創設を本部に委託され、帰国後米山の協力をあおいで1920年10月に東京ロータリークラブを創設した(チャーターメンバーは会長米山梅吉、幹事福島のほか深井英五、磯村豊太郎、星一、樺山愛輔、牧田環、佐野善作、和田豊治など24名)。滞米の終わりにはダラス・カントリークラブ(ゴルフ)にも入会を許されたし、自家用のフォードを持ち、兎狩りや汽船でのまぐろ釣りなどもするほど豊かでアメリカ社会に溶け込んだ。渡米当時の東洋人蔑視の風潮の中で、多くの屈辱を味わった経験もあったらしいが、それをのりこえて米国社会の内部に受け入れられた実績から、米国の友人も多く民主主義や自主性尊重の良さを十分評価していたはずであった。
事実その家庭内では当時の日本では異例な民主主義で、十二才年が若く自由闊達な母を尊重して、子供たちを自由主義、放任主義で教育することを認めた。我々四人の息子は特別の家訓も受けず、幼稚園や塾の教育も受けなかった。
1932年に暗殺された蔵相井上準之助が日本銀行当時訪米した際案内をしてその深い信頼を受け、自分も尊敬して見合いの仲介さえ依頼し、仲人も頼んだ。どちらかというと政治嫌いで、とかく腐敗の噂がつきまとっていた東京高商同窓(一年おくれ)の内田信也(1880~1971)(後に岡田内閣の鉄道大臣)には強く批判的だった。家庭には米国から帰国して後も神棚、仏壇、父母の位牌をもたず、西本願寺系の菩提寺、墓が佐賀県なので寺詣りもしなかった。
神社に行けば礼拝はおこなっていたが、少なくとも満州・上海事変当時までは神仏信仰への深い関心はなかったようだ。
二・二六事件の前後には北吟吉、西田税、若干の陸海軍中堅青年将校たちとの交際があった。
私は自宅に西田税が訪問してきた姿を見ている。また父の机上に北玲吉の七百円の借用証書が放り出されていた。何故そんなものを粗末にしていたのか不可解で、返済の可能性のない献金だったのかと推測する。
事件前後に激しい電話の会話が続き、当時コンニャク版といわれたコピーものの軍部、右翼の内部情報が大量にどこからとなく入っていた。そのころから政治的、思想的には蓑田胸喜(1894~1946,自死。元慶応大予科教員)、 三井甲之(1883~1953,元山梨県敷島村長)らの原理日本社(1925~)、帝国新報社、野依秀市(1885~1968)の実業之世界、帝都日日新聞などの出版物に強く影響されるに至った。
その非合理的思考、たとえば物理学の定説などを頭から否定する主張などを熱烈に支持して、大学で物理学を専攻する兄に議論をふきかける姿は異様で、帝大系統の西欧的合理主義に深い敬意をはらう学統には全く敵対するものであった。
さきの矢次一夫の『昭和動乱私史』によると昭和8年12月28日に発起人会を開いた国策研究会の会員名簿に父の名がある。また昭和11年11月25日に改組した同研究会の創立総会にも出席している。
三井の財界活動の使命を託されたのだろうが、1937年4月末に日本経済連盟会が米国、英国等に派遣した経済使節団に三井を代表して参加した。
その顔触れは次のようなもので、当時の財界で有力なメンバーだったといえるだろう。
団長 門野重九郎(東京商工会議所会頭、大倉土木会長)
団員 福島喜三次(三井合名理事)。夫人同伴は以上二人のみで、英語会話力とあわせて、事実上の副団長であった。
石坂泰三(第一生命取締役)
木日木中寺出島柏春鈴田小下高秀茂(正 金銀行東京支配人)
弘(住友本社理事)
祥枝(東京海上火災会長)
寛三(三菱商事会長)
源吾(大日本紡績社長)
義雄(名古屋商工会議所副会頭)
誠一(日本経済連盟会常任理事)
随員 以上の団員がそれぞれ一名の若手秘書を伴った。
そのなかで父は最も英語会話にすぐれ、米国財界に既知も多く、団長を助け、約2ヵ月の米国旅行の各地の全ての団長演説原稿を一人で引き受けて作成するなどの激務を果たして過労となった。そしてついに7月渡欧後に結核を発病、10月半ばに帰国後一年休職することになった。
対照的にその12月向井は三井物産の代表取締役に就任した。父はその後一旦は復職したものの、すぐ病状が再発して昭和15年8月三井総元方に改組した後の理事を退くことになった。その時の総元方専務理事は向井であった。生涯あくまでライバル的立場にあったのは因縁であった。両者に公然の対立があったかどうかは詳らかにしないが、その経営思想が全く異質だったことは明らかである。
戦争末期から敗戦の実態は当然理解していただろうし、「承詔必謹」(天皇の詔勅を受けたら無条件にそれに従うという意味で当時政府が強く国民に求めた言葉)が何よりの支えだったのだろう。
やがて療養先の三浦半島にも米兵が進駐を始めると、たちまち二十五年前の米国時代 の経験を蘇らせて、"offlimits"、"warrantofficer"などの米軍の新用語の語義や、米軍の指令、行動に深い興味や理解と、時には好意を示した。
米国を知らない若い私の方がかえって反米的でこの態度についてゆけず急速な転身に呆れる思いだった。
戦時中自己の信念に殉じて、全資産を軍需企業の株券と国債に投入し、生活費はそれらを担保とした銀行からの借入金で賄っていた。敗戦により国債、株式がほとんど無価値になって、破産状態に近い中での死であった。もちろん戦災による資産の喪失は珍しくない時だった。
幸運に家屋の戦災を免れ、いわゆる「たけのこ」生活で手放す家財が残ったのは、はるかに恵まれていた方であろう。私が銀行と協議して負債の返済を僅かな繊維その他の株の売却でやっと済ませた報告を喜んで聞いたが、 その翌日台風襲来の最中に亡くなった。
占領政治との交渉
占領下になって配給に米軍の野戦用缶詰その他の保存食品が与えられ、駅にMP(憲兵)がいて、発疹チフス予防用に改札口の木枠の上に立って、男女の区別無く通過する乗客の肩から首筋に強制的にÐDTを真っ白にまきかける。道路は米軍のジープばかりが我が物顔にかけまわり、空はもちろん米軍機ばかり。国電には米軍専用車両があり、いつもガラガラでGI(govemmentissueの略で、官費の服装、生活をしているという意味から兵士を意味した)が、ガールフレンドにした日本娘を連れて座っている。日本人はボロボロの車両にすしづめという風景。
罹災地の後片付けには米軍の強力なブルドーザーが働く。これらを疲れ果てた日本人が呆気に取られて莚然と眺めているというのが、当時の東京の姿であった。
しかしそれらを除くと私のように反米的意識を容易に捨てられなかった個人が米兵と接触する機会は意外に少なかった。
この頃の私が占領政治をどのように認識し、どんな印象を受けていたかを示す事例をかえりみておこう。
東大では、戦後開講した労働法の講義があり、末弘厳太郎教授は昭和初年の欧米留学で労働法学を日本に持ちかえって開講しようと試みたが、当時の政府につぶされて挫折した。教授は戦時中私の在学当時の法学部長であった。
その頃なんと東大の入学式には「父兄同伴」が求められていた。病床の父の代わりに出席した東大物理学科を卒業した兄は、末弘法学部長が訓示して「今は科学万能のようなことを言っているが、理科を出た人間に国家を運営することは出来ない。法科で学ぶ諸君が天下国家を担わなければならない」と激励したので憤慨していた。
私達の軍事教練の野外演習にも、国民服、戦闘帽姿で出席して訓示を行い、学徒出陣の壮行会の時には「『行ってまいります』は生還を前提にした言葉だ。帰ることを考えず に『征きます』と言え。」といわれて気が引き締まったことを覚えている。
そんなわけで学生の眼にはかなり戦争協力的に見え、一部学生は批判的だったが、私は好感を覚え、矢部さんのように軍部に迎合した人とは立場が違うと感じられた。末弘さんは戦後直ちに労働法講座を復活させ、1946年5月ころに新設された中央労働委員会と東京地方労働委員会の第三者委員となり、委員長の三宅正太郎元大阪控訴院長が追放となった後、委員長になった。
しかし戦時中の言動が占領軍に通報されたのか、たしか大日本武徳会の役員だったとの理由で教職追放になったと思う。ところが公職追放にはならなかったようで、労働委員会の委員長(後に会長)は継続し、労働者委員の徳田球一(共産党)や荒畑勝三、松岡駒吉、西尾末広、鈴木茂三郎(社会党)、使用者側の膳桂之助(日経連)などとわたりあい、その信頼をかち得て、その後長く労使紛争の火中の栗を拾い、労働法の実践にその余生をささげた。
占領軍兵士との接触
45年の秋の一日、東横線の事故にあって車内で長時間足止めをくった。たまたま隣に占領軍の下士官がいて(専用車がなかったと見える)事故の話から占領下で初めて米兵と会話をかわした。英語を使って外国人と会話したのも、戦前から初めてだったと思う。単語を思い出すのに骨をおりつつ、スミスを勉強した知識を活用して日本の現状を説明し「日本の農民は平均2エーカー程の農地しか保有していない。米 国と比較してどんなに苦しいか分かるだろう」といささか抗議口調になった。するとすかさず「お前は東条が好きか」と逆襲してきた。やっぱりこう来るのかと鼻白みながら(hateといっては強いかなと迷いながら、dislikeとは思いつかず)「IhateT6j6」とかわす。「明日GHQのこれこれの場所に自分を訪ねて来い、もっと話そう」とさそわれた。
どうやらこいつは周りのシッポをふる奴と違って面白そうだ、使えるかも知れないと見られたらしい。わりに知的な男だったから訪ねて実情をもっと細かく訴えたいという気持ちも動いたが「戦勝国軍人にやすやすと尻尾をふるものか」と片意地をはってそれきりにした。
もし訪ねていたら私の運命は変わったかなと、その後時々思い出した。何しろ当時生活のために最も得やすい職場は占領軍の通訳やPX(軍人用販売店)だった。親友早川も郊外の洋館を米兵に接収されて、その縁で立川基地の通訳に入り、通称はっとむをちじめてTomになったと平気で語るのが情け無い思いだった。彼はそれから米国関係に縁づいて晩年は長く米国銀行に勤めた。外国育ちの従姉も、外務省の元同僚もPXに働いていた。その人達に花瓶や着物などの家財を売る取次ぎをよく頼みにいったが、不思議なことに占領軍兵士との対話は経験しなかった。そんな心境の頃 『世界』の46年2月号 に一高のドイツ語教授の竹山道雄氏が米兵との交遊をヒューマニスティックに描いた「交歓」というエッセーを読んで割り切れない気持ちを抱き、卑屈ではないかといささか詰問的な手紙を送り、弁明の返事を(惜しいかな、紛失した)いただいた事があった。先生はかなり不快であったろうと今は気が咎める。
戦争犯罪の問題
ポツダム宣言にも予告された戦争犯罪人の処罰問題が45年秋の大きな話題になっていた。当時欲を出して顔を出してみた上智大学でのラテン語講習会の機会に米国のキーナン主席検事が講演したのを聞いて関心を一層そそられた。一年位後に社研の塩田庄兵衛君が知人の弁護士から市ケ谷国際法廷のA級戦争犯罪人審理の傍聴券を入手してくれて、後年労働経済の大家になった氏原正治郎君と三人で実況を見ることが出来た。その日の審理はソ連検察官の出番で、あまりドラマティックな場面はなく、法廷のメチャメチャに(米国的水準だったのだろうが)明るい照明と、審理に参加する連合国各国の色とりどりの国旗をずらりと後ろにならべた裁判官の席などまるで歌舞伎の松羽目の舞台を見るようで、その政治的演出を強く感じとることになった。
ここに俘虜虐待問題をとりあげて、友人のために国際法の卒業リポートを書いた原稿が残っている。大学に復帰して久々に図書館を利用したものだったらしい。このリポートは、大学在学中の国際法研究の成果を反映して、形式的には一応整っている。だが問題の本質を深く考えるには至っていない。後のソ連抑留捕虜の問題もあわせて考えると、ジュネーヴ条約の人権擁護の規定の重要性を今知ることが出来る。国際法学は当時このような形式論で固まっていたという気がする。イデオロギー的には私がBC級の軍事裁判に対して、強い反発を持っていたことを示しているが、実際のBC級裁判でこのような形式的な法理論の弁護を展開する余地は無かっただろう。現実には占領軍の強引な審理が進められたのだろうが、実際の資料をフォローする余力がない。唯その報道を見るころには、被告と米国側の証人との醜い責任転嫁の論争がクローズアップされて、正義の論議は影も無く、被占領国民の無力感に押しつぶされていた思いがある。周囲の友人と理論的反発を語りあう気力もなかったらしい[この問題はたまたまイラク戦争で再現しつつある。多少参照の価値もあろう]。
三章 社会へ1947
学校を出る
中学時代から母方の祖父杉村溶(1898年の朝鮮閲妃殺害事件の時大使館一等書記官で事件の計画にたずさわったとみられる。1906年ブラジル弁理公使の時任地で病死)、伯父杉村陽太郎(1927-33年国際聯盟事務局次長兼政治部長、その後イタリアに次ぐフランス大使の時ガンを発病、帰国後死去)のあとを継ぐ外交官の道を志望していた私は敗戦により目標を失った。戦後の食糧難とインフレの窮迫期で、ヤミ商売を除けば食べてゆける仕事はなく、求職は選び放題だが、どの産業、どの企業にも未来を感じられない時代だった。
特に軍隊で結核を患って、その再発を恐れる身体で殺人的な交通マヒの中、毎日満員電車で通勤する自信はなかった。
東大法学部だったから当然友人が次々官庁に入った。また時代の指針と見られた出版社に入ってゆく人もいた。しかし母が結核で倒れた家庭で、三人の兄は就職して忙しく、私が専ら家族の食事、洗濯、買い物などの雑事を引き受けていたから多忙な日を送り、自分の終生の道をどこに求めるか悩んでいた。
戦時中の外務省で役所勤めにはこりた。当時「(教師に)でもなろうか、(教師に)しかなれない、でもしか教師」という自嘲、ひやかしの言葉が流行っていた。
未来にかける教師は食えないので希望者が少なかったからだ。学徒出陣の時に仮卒業を拒否したので、残した七科目をとらなければいけないと誤解していたことも頭痛の種だった。
一一九四六年末の東京帝国大学新聞で新設の社会科学研究所の助手募集の公示を見つた。
未だ設置の場所もきまらず、航空研究所の跡地(渋谷区駒場の現東大教養学部の裏にあ り、当時占領軍指令で廃止がきまっていた。現東大宇宙科学研究所)に置かれるかと予想されていた。
それなら自宅から徒歩三十分以内で通勤できる場所であり、研究機関なら勤務にも比較的余裕がありそうで体力的に耐えらるかと思えた。調査は外務省でも多少経験し、やれるかも知れない。当たって見ようと、とにかく法学部事務室に書類を求めに行った。するとまず戦時の仮卒業の条件で単位を取らずに卒業が出来ることが分かった。幸 い「学徒出陣」前の学業成績は良くて、応募の資格は十分だ。これなら法学部助手にもなれるから、そちらを志願すれば良いとすすめられた。確認しなかったが、その人は多分南原教授の弟子の一人で後に中大教授となった小松春雄氏だっただろう。
だが私の東大法学部教授の学識、才能への信仰は未だ強烈だったので、戦時教育で未熟のまま「仮卒業」する身には法学部などとても近寄り難かった。
一生かけて調査研究の下働きをやっていれば、何か仕事ができるかも知れない。またその中に戦後急速に脚光をあびたジャーナリズムを通して、民衆啓蒙の仕事も開けるか。戦時中、米国の実情を知らずに開戦した日本の軍人、政治家、官僚。
開戦後も戦争政策に国民の総力を集中統合できなかった政治のありかた。これらの原因をつかむべく、日本の政治の実情を研究したいとの念願が強く、高度の理論教育に専念する法学部より社会科学研究所の方が目標に近いと思えた。
初めに既に法学部で岡義武先生(日本政治史)の助手になっていた一高の同級生横田地弘君(後学習院大教授、欧州政治史)に話を聞きに行ったら、社研所員でやはり一高文丙の先輩、日本政治史の林茂先生を紹介された。
訪ねると今度は矢内原忠雄所長に会いなさいとの勧め。
戦時に多少の社会経験を積んで度胸が付いた私は平気で経済学部の二階の日当たりのよい研究室に突然訪問した。脱いだ外套を手にかかえ、先生の机の前に直立して応募の心得を質問した。
先生は笑顔で気さくに話に応じてくださって、その態度にすっかり嬉しくなり、次第に一高で先生と同級だった伯父杉村英三郎(陽太郎の弟)のこと、自分の兄たちが神戸一中で先輩としての先生の講演を聞き騒いで叱られた話など話し込んでしまった。
先生は論文を書く時は引用文献を明確に示すことを厳守するようにという点だけ注意された。
「政治学について」
年末から生まれて初めて与えられた課題なしに自分でテーマを決める論文というものを書くために東大図書館に通った。
目標は政治研究なのだが、どこから手をつけてよいのか分からない。東大法学部の『国家学会雑誌』のバックナンバーをまず手掛かりに次々政治学に関係のありそうな文献を読み漁った。
しかし探しても探しても私の思うような日本政治を分析した業績は見つからない。当時すでに論壇の主流となったマルクス主義文献の参照は不可欠であろうと考えたが、探し方が悪かったのか、未だ戦時中の閲覧禁止処分のカードの回復が十分でなかったのか見当たらず、かろうじて三木清や戸坂潤の論文を多少閲覧し、佐々弘雄の論文にいくらかそれ らしい文献が引用されているのを見つけ、それを参照することが精一杯だった。
当時のポケット日記に記された読書メモではその頃やっと堺利彦訳「共産党宣言」,エンゲルス 「空想的及科学的社会主義」,マックス・ウエーバー「職業としての学問」,「社会科学と価値判断の諸問題」,タルド「社会法則」,リッケルト「文化科学と自然科学」,蝋山政道「政治学の任務と対象」,大山郁夫「政治の社会的基礎」,堀豊彦「中世紀の政治学」,大類伸「概論 歴史学」などを読んだにすぎない。
戦時の学生時代から遡ってみても、政治学関係といえそうなものは、『アメリカの外交政策』アンドレ・モーロア、『フランス破れたり』滝沢敬一、『第四仏蘭西通信』芦田均、『日本近代外交史』ドーソン、『政治の彼方に』G.F.ハドソン、『世界政治と東亜』H.M.ヴァイナック、『東亜近世史』金井章次、『満蒙行政項談』『ル ーズベルト政権十年史』『井上馨伝』『伊藤博文伝』『懐往事談』『日本文化史序説』小松緑、『錦旗を続りて』『法哲学 』『大隈伯昔日談』『実定法秩序論』『ビスマルク書簡集』くらいなものであった。
馬鹿々々しい大串兎代夫『国家学研究』などという代物も高文に必要などと聞いて眼をとおしていたのはいまいましい。
そのあげく特に蝋山を読んで過去の所謂政治学なるものは、まるで私の構想するものとかけはなれていて、現実離れした方法論や政治概念論の抽象的論争に終始していたことが段々分かってきた。
最も実践的だった大山郁夫にしても、とても日本の現実政治を分析しているとは思えなかった。結局論文は「政治学について―その対象と方法の一考察」と題して、その過去の状況を批判的に描きつつ、政治の概念とは何かを考察し、最も通説的と考えられる概念を「平均的概念(矢内原さんに「平均」には統計学の厳密な定義があると批判を受けて後に中間的と改めた)」と名付けて示した400字26枚、参照文献と注が10枚ほどの小論文をまとめただけに終わった。
ともかく約三ヶ月たらずの苦闘で私は初めて、当初自分が考えもしていなかった論旨が一篇にまとまるという、未知の創造の喜びを感じる満足だけは味わった。
この論文はその後発表の機会を得ず、1976年になってやっと専修法学論集』22号に書いた「政治学の課題」という論文の附論(p。68~85)として発表した。
その一部を抄録しておこう(抄録なので注は省略する)。
「一序」では「敗戦後の今日、社会科学の必要くらい痛切な要求はない。もとより学問は必要のみに奉仕するものではなく、かかる傾向はむしろ学問を邪道に導くものであることはいうまでもない。が、いかなる自立的の学問でもその始原的要求は学問のための学問ではなく、むしろ人生のための学問であったことは疑えないものだと思う。……」「我が国の社会科学の中でも
一一・政治学のふるわぬことはいちじるしいものがあるように考え られる。おこがましいことをいう資格はないが、これは近時の弾圧に基くばかりではなく、政治学自身の混乱にも基くものと考える。すなわち本来実証的なるべき政治学が、古来の悪弊たる形而上学的独断的教説にまどわされていた形があるので はなかろうか。もとより学問の困難と自己の無力とは十分知るが、あくまで事実に即し、事実に学んで政治学を考えてみたいと思う。
§9 戦後の旅行事情・原爆後の復旧
その社研の面接試験の直後、私は大旅行を計画した。当時交通機関の崩壊で旅行が極めて困難であったにもかかわらず、これから世界の政治を考え、政治学を研究するには、まずヒロシマの原爆被害を直接観察しておくことが不可欠だと考えた。家計も苦しかったのに母が支持してくれた。
私達一家は14年前まで神戸東郊の御影町に約12年居住した。小学校5年を終えて東京に転校した後その事実上の故郷を訪れたことはなかった。戦後経済界追放にあった母の兄も東京を去り大阪で勤務するようになって数年経っていたから、母にはその消息をたしかめさせたい気持ちもあったのであろう。窮迫の時代にのんきな話のようだが、この当時はよくぞ戦争を生き延びたという感じが強く、親族や旧友の安否を確かめたり、自分の生を回顧し今後の生き方を真剣に考えたいとの思いが強かったのである。
七日目やっと11時広島着、中学の親友に案内されて午後4時まであいにくの強風のなか町を歩く。その後一人になって広島城を初めとして市内を飛び回り、深刻な印象を受けた。翌日7時半にはもう広島を発ち夕方5時三宮に着いた。
広島は被爆から一年半を経過していたが目抜きの通りの両側には、主として飲み屋のバラックが立ち並び特に米兵めあてのパンパン(当時インドネシア語の女の読りとかいうこの言葉が売春婦の呼び名となっていた)宿がやたら目についた。しかもその裏は全く手つかずの瓦礫の山であった。これは1972年に那覇市を訪れた時、目抜きの平和通りの直ぐ裏が瓦礫の山のままになっていて、驚いたことがあったから、一年半後では当然のことだっただろう。有名な福屋デパートの焼けビルに上って見ると"Kilroywashere!"と米兵が落書きした黒々とした文字が屋上の壁面を埋めて、何とも言えぬ哀愁を感じさせた。Kilroyとはてっきり悪魔をいみするのだろうなどと勝手に解釈していた。
これは`ASupplementtotheOxfordEnglishDictionary.Vol.2,1976.'によれば、「第二次大戦中米兵が世界中で落書きした、神秘的な人名である。」その意味は不明のようだが、戦時中ベスレヘム製鋼会社のドックで戦艦のタンクや二重底などの検査をしていたKilroy氏が検査官への証拠のためにそう書いたのが急速に…般に伝播したのだとの説もそこに記されている。私はすでに東京の神宮外苑の絵画館の壁あたりに書かれたものを見て、従兄の柴 田南雄から由来は聞いていた。
崩れたデパートの屋上から眺めた広島は未だ完全に焦土の都市であった。そこを離れて西部軍司令部があった広島城祉に着いたのはすでに夕方だった。人影もないそこに、驚いたことに自分も陸軍病院で使った、陸軍の青い星の記章付の瀬戸物の飯碗と皿の類の破片が、まるで今支度が出来ましたというように整然と横に二列をなして向き合って散乱していたのである。ちょうど兵舎で食卓に準備が整った時に原爆が炸裂したのであったろうか。しかもよくあたりを見ると瓦礫の中にまだ細かい白骨の残片がたくさんまじっている。ぞっとしながらさらに見回すと脇の瓦礫の中に白いものが風にひらひらひるがえっている。
何かと思って一つを拾い上げて見ると、それは美濃紙に細かく記入した兵籍簿であった。陸軍で各中隊事務室で管理・保管していた、在籍兵士の戸籍、住所、家族などを記したものに間違いなかった。
その時は一体こんなことがあり得るのか、被爆して紙が焼けず、しかも一年半も風雨にさらされ、そのまま片付けられずに残存しているなんてと、総毛立つ思いで眺めた。今思えば資料としてそれを保管すればよかったとおもうが、とうていそれは出来なかった。今も幻覚のような気がする。
しかし兵隊の氏名や本籍などをカーボン紙をあてて鉄筆で書いたものがはっきりと読み取れた事に間違いはなかったのである。
--すでに被災者はめったにいない事を知った。多くは戦後移住した人達であった--
私はこの短い滞在の間に市内のあちこちで市民に原爆被災直後の状況を質問して歩いた。その間にすでに被災者はめったにいない事を知った。多くは戦後移住した人達であった。また何人かは「そんなことを聞いていると米軍のMPに連行されるぞ」と脅かした。東京ではそんな事情を全く知らなかった私には十分恐怖をあたえた。そんなことで、別の人が「比治山の原爆病院に行ってすさまじい傷痕の被爆者を見て来なさい」とすすめた時には臆病になって実行できなかった。長く心残りであった。市内を歩く限り被爆者の姿を見ることはなかった。
相生橋の欄干が無残に倒れている姿や、原爆ドームの有名な鉄骨、人影だけ残った銀行の石段などは見た。しかし聞き取りをやった目的は何とも恥ずかしいことだが、今後再び原爆攻撃を受けるとしたら、どんな対策を講じておけば良いかという戦略的視点であった。
つまり米国の被爆者調査とほぼ同じで、原爆戦争は避けられないものとした上で、どうすれば被害を予防できるかと考えていたのであった。聞き取った印象は、意外に罹災直後の復興対策は順調に行われたのではなかったかということである。
ノートに残されたメモを見よう。
『市内電車〔生き残りの乗務員の話〕。紙屋町一宇品。四日後。5、6台 。護国神社前の変電所が壊滅。本社変電所、本社内車庫、宇品方面で電車100台中5、6台残った。47年4月になお40台しかない。以前より人員も減って44~45人。己斐方面の河は舟で連絡した。乗務員は100人中60~70人残った。女学生の勤労動員の者もいた。被爆後全員出勤、その為に死んだ者もいた。しかし恐怖心はなかった。本社内(鉄筋コンクリートの建物で無事だった)で死んだ者は無し。被爆者の発掘をした。それで横川線の者も2、3日内に死亡した。線路、道路は被害がなかった。架線と電柱の被害。
一般の被害だが3、4日は燃え続けた。その間雨無し。配給は炊き出しで不自由はなかった。
食券を発行した。
国鉄は一昼夜で開通。客車、線路障害。軍用ホーム、枕木焼ける。延焼で駅燃える。(駅での)死傷数名。欠勤者1/3くらい出る。疎開者一週間位で整理。小荷物、戦災者のみ行った。
3、4日後。10月ころ完全復旧。向洋は3日後に開通。
比治山公園の東は家屋が残った。終戦まで三原辺り(東へ18里)では(機密保持の為原爆被害の)実情を知らなかった。
〔一般〕宇品辺りでは北面屋根はすべてくずれているが、家屋倒壊は無いらしく、南面のガラス窓は割れていないものもあり。モルタル壁の家等ガラスの外、北壁も被害無し。白壁はくずれたもの多し。
〔郵便〕8月10日に貯金再開。貯金支局が壊滅した。郵便は記憶がない。
〔新聞〕朝日は当日五日市から乗り込む。自動車で出て連絡した。
〔電気〕9月(復旧)。8月末には電灯会社のみ。変電所は大手町、千田全焼 。段原軽微。大須発電所一部被害。
〔市役所〕1/3翌日出勤。一部事務。女子は全部休む。補充翌年。重要書類は疎開ずみ。 出勤者にガラス等の被害。』等とある。
この時現場を見ておいたことはその後長く参考になった。占領下ではほとんど報道が禁止されていた実情はかって「原爆情報の疎外」と題し『平和研究』9号(1985)に書いたが、講和発効直後に『アサヒグラフ』が原爆被害写真の特集を発行したのが、広く目にふれた最初の出版物であったはずである。1950年の東大五月祭の時、社研職員組合の名で見物人に原爆のアンケートを取り、丸木位里・俊さんの原爆デッサンの小パンフレット『ピカドン』を配ったことがあった。しかしその回答は祭りの終わった後のこととて発表方法がなく、東大のアーケードに小さなポスターを貼ったけに終わった。その記録は残っていない。
むすび
戦後体験はまだ続くが、学生時代を一くぎりとして終わる。その後の体験は、機会があれば私の政治研究を中心にまとめる事が出来ればと考えている。自分自身の意識転換については、その後の長い年月をたどっても説明がつけられない予感がある。このような形式の記録の発表を許して頂いたことを厚く感謝する。
(1994年8月起稿、2003年1月21日脱稿)
├
├福島新吾 社会科学としての政治研究―1947~54(専修大学社会科学研究所月報)
『専修大学社会科学研究所月報第 478 号』に「体験戦後史 1945~47」と題して敗戦後の体験などを述べた。引き続き発表の機会を与えられた事を深謝し、私の研究者としての出発期を回顧したい。私はこの国に初めて創立された東大社会科学研究所の助手となった(公募第一期)ので、その研究所は当時如何なるものであったのか、そこでは社会科学をどのように考えていたかをふりかえる。この研究所のお蔭で私の政治学研究には社会科学という frame of reference が加わった。私はそれを十分政治学に生かしたとはいえないが、少なくとも同世代の狭義の政治学者とはかなり違ったテーマ、視角、展望をとったと思う。そのいきさつが社会科学の発展史の参考になればと願う。他方世界政治の変遷とその日常生活への浸透にもまれつつ私の政治意識-国家意識あるいは愛国心-が変わっていった経過もふりかえってみたい。
目次
はじめに ································································· 1
§1 東大社会科学研究所 ················································· 2
§2 その組織と活動 ····················································· 5
§3 社会科学をめぐる対立 ··············································· 9
§4 私が経験した調査・研究活動 ········································· 11
① 無産政党の選挙結果 ··············································· 11
② 労働組合の調査・研究 ············································· 12
③ 選挙の実態調査 ··················································· 13
④ 公安委員会調査 ··················································· 14
⑤ 農村調査 ························································· 15
§5 理論と実践 ························································· 18
§6 社会的活動 ························································· 20
編集後記 ································································· 24
├
├福島新吾 - Wikipedia
├
├福島喜三次 - Wikipedia
福島喜三次(ふくしま きそうじ、1881年〈明治14年〉10月10日 - 1946年〈昭和21年〉9月17日)は日本の実業家。三井合名会社理事。内閣調査局専門委員及び企画院参与を務めた。日本人初のロータリアンで、元ダラスロータリークラブ会員。佐賀県西松浦郡有田村に福島喜平の六男[2]として生まれる。2歳のとき父を亡くす。小学校時代から終始級長を務めるなど秀才で鳴らし、長崎商業学校(現・長崎市立長崎商業高等学校)を経て、1904年(明治37年)7月に東京高等商業学校(現・一橋大学)を首席で卒業。同期には星野唯三、園部潜、佐藤尚武、山崎一保、向井忠晴、黒田慶太郎、梁瀬長太郎らがいた。なお、同校では上級の優等生を選び夏季休業中に実地研究を課したが、福島も3年次に選ばれ「清国上海ニ於ケル貨幣事情調査報告書」を提出している。1904年に三井物産入社。門司支店に配属された後、清国への赴任を希望していたが、1905年(明治38年)3月にニューヨーク支店勤務となり、1906年(明治39年)からは出張員として、オクラホマ州及びテキサス州へアメリカ綿の現地買付に従事。戦前期には政治にも関わり、国策研究会の第一研究委員会(外交・国際関係)メンバーとなり、1935年9月に岡田啓介内閣の内閣調査局専門委員、1937年(昭和12年)6月には第1次近衞文麿内閣の企画院参与に任命された。1937年に日本経済連盟会(経済団体連合会の前身)の欧米訪問経済使節団(団長門野重九郎)メンバーとして派遣されたが、過労で結核に倒れ、帰国後に休職・引退、第二次世界大戦後の翌1946年(昭和21年)に没した。
├
├佐藤尚武 - Wikipedia
佐藤尚武(さとう なおたけ、1882年(明治15年)10月30日 - 1971年(昭和46年)12月18日)は、日本の外交官、政治家。林内閣外務大臣、第二次世界大戦末期のソ連対日参戦当時の駐ソビエト連邦大使、戦後には参議院議長(第2・3代)等を歴任した。旧弘前藩士で当時大阪府警部であった田中坤六の次男として大阪府に生まれる。同じく弘前藩士で外交官の佐藤愛麿(後に在米特命全権大使)の養子となる。旧制正則中学校(正則高等学校の前身)卒。1904年(明治37年)、東京高等商業学校(一橋大学の前身)全科卒。同専攻部領事科へ入学。一橋では同級生の向井忠晴(三井総元方理事長や大蔵大臣を歴任)や福島喜三次(元三井合名理事)と首席を争った。1905年(明治38年)、外交官及び領事官試験に合格し外務省入省。在ロシア公使館外交官補(のち三等書記官)、ハルビン領事(のち総領事)、在スイス公使館一等書記官、在フランス大使館参事官、在ポーランド公使を歴任した。参議院議員選挙区青森県選挙区在任期間1947年5月3日 - 1965年6月1日。
├
├向井忠晴 - Wikipedia
向井忠晴(むかい ただはる、1885年1月26日 - 1982年12月19日)は、日本の実業家。太平洋戦争期における三井財閥の指導者。三井物産会長、三井総元方理事長。東京市生まれ。開成中学校を経て、東京高等商業学校(現一橋大学)本科卒業。一橋ではテニス部で選手として活躍したほか、学業においては同級の佐藤尚武(元参議院議長)や福島喜三次(元三井合名理事)と首席の座を争った。第56代大蔵大臣内閣第4次吉田内閣在任期間1952年10月30日 - 1953年5月21日。
├
├(83) 「日米開戦不可ナリ」|ストックホルム 小野寺大佐発至急電 - YouTube
├
├小野寺信 - Wikipedia
小野寺信(おのでら まこと、1897年〈明治30年〉9月19日 - 1987年〈昭和62年〉8月17日)は、日本の陸軍軍人、翻訳家。最終階級は陸軍少将。1897年、岩手県胆沢郡前沢町(現在の奥州市)において町役場助役・小野寺熊彦の長男として生まれる。12歳の時に熊彦が病死し、本家筋の農家・小野寺三治の養子となる。遠野中学校、仙台陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、1919年(大正8年)5月、陸軍士官学校を卒業(31期、歩兵科。歩兵科5位で恩賜の銀時計を拝受。
├
├大島浩 - Wikipedia
大島浩(おおしま ひろし、1886年(明治19年)4月19日 - 1975年(昭和50年)6月6日)は、日本の陸軍軍人、外交官。最終階級は陸軍中将。第二次世界大戦前から戦中にかけて駐ドイツ特命全権大使を務め、日独伊三国同盟締結の立役者としても知られる。終戦後の極東国際軍事裁判ではA級戦犯として終身刑の判決を受けた。陸軍士官学校、及び陸軍大学校を卒業した陸軍軍人であった。1921年(大正10年)、駐在武官補として初めてドイツに赴任、ナチ党とのあいだに強い個人的関係を築くようになった。1938年(昭和13年)には駐ドイツ日本大使に就任、日独同盟の締結を推進し、1940年(昭和15年)に調印された日独伊三国同盟も強力に支持した。終戦後にはA級戦犯として終身刑に処せられ、1955年(昭和30年)まで服役した。
├
├御前会議 太平洋戦争開戦はこうして決められた
├
├
├
├
├
├
├
├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年05月02日号「日本計量新報週報デジタル版」
├
├2020年08月18日 文武両道は集団催眠がもたらした言葉だ | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)
├文武両道は集団催眠がもたらした言葉だ
├
├2019年03月23日 土曜日の朝、ガストで朝定食を食べる。新聞を読む。逸ノ城は一敗のままで優勝争い。
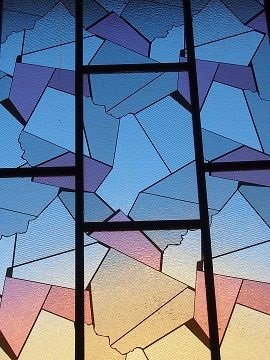
写真は別所温泉ホテル南條のステンドグラス。
金曜日の3月22日は暖かい日で東京は桜が咲いていた。翌日の土曜日は寒くなった。ミゾレのような雨が降った。曇り空に気持ちが塞ぐ。
音楽を聴いて後、ガストに出かける。ガストでは朝定食を食べる。新聞を読む。逸ノ城は一敗のまま優勝争い。新聞にはそのように書いてあった。
├
├2015年12月13日 日本に飛んでくる黄砂は万里の長城の煉瓦を焼く森林伐採によって生まれた。
├
├音楽を聴く 音楽家と演奏